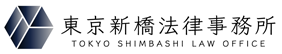目次
■はじめに
・単発型
・返品特約
■裁判例
■まとめ
■はじめに
個人向け事業を行っていく上で頭の痛い問題の一つがお客様からの一方的なキャンセルの取り扱いです。
普通、何らかの約束がされた場合には、それを守ることが義務となり、法的に意味のある「契約」にあたれば、裁判所の力を得て、その義務を強制することさえ可能となります。
ですが、個人が企業と約束した場合、キャンセルできて当たり前と思っている方が少なくないようです。特に口頭での約束やWEB上での申込みでは、その傾向が強いと考えられます。
本来、契約は守られるべきものです。
ですが、過度にお客様を縛りつけることで、かえって企業のイメージを損ない不利益となることもあります。
バランスを取ることが重要といえます。
不測の損害を回避しつつ、企業のイメージを維持することが一つの目標となります。
そのための代表的な対策が、キャンセルが起きたときに備えた規約の作成です。
ここでは、キャンセルに関する問題について解説していきます。
■ポイント1~概要
・問題点
ホテルや旅館の宿泊、レストラン等の飲食、WEB等の各種サービス、インターネットや雑誌の通信販売など、さまざまな個人向けのサービスが存在しています。
ビジネスにおいては売上をあげることも重要ですが、売掛の回収も重要です。
特に一件あたりの債権額が小さい場合、催告しても無視され、泣き寝入りする人も多く、そのことにつけ込んで常習的に踏み倒す人もいます。
そのため、確実かつ効果的に回収する方法を考えていく必要があります。
具体的には、契約の仕方やその内容、決済の方法等を工夫していくことが考えられます。
一方で、サービスを提供する側とそれを享受する側とでは専門知識や、交渉力などに差があることも確かであり、公平な取引のためにハンディキャップが課されています。
・消費者契約法
ハンディキャップの代表例として、違約金の制限があります。
契約を解消すると不利益を被ることがあるため、これに備えて賠償金額をあらかじめ定めたり、心理的に圧力を加えたりするために、約束を守らなかったらお金を支払う旨の約束をすることがあります。
ですが、その内容があまりにも不当なことがあるため、規制がされているのです。
具体的には、「解約に起因する損害額の平均」に制限されます。これを超えるとその分が無効にされます。
また、解約を一切認めないなど、一方的に利用者を害するような内容も認められていません。例えば、学習塾や資格試験の受講契約は準委任契約にあたりますが、この契約は一方の当事者からいつでも解消できるとされており、これを否定すると問題になりえます。
最近では、消費者団体による手続きも可能となっており、個別の利用者に代わって法的な手続きが行われることも増えています。
特に、2016年に施行された特例法により金銭的な請求も可能となったことから、多額の返還請求を受けるおそれが高くなったといえます。
したがって、個々のキャンセル料が少額だからといって、不相当に高額とならないように注意が必要です。
・特定商取引法
電話や訪問による勧誘販売についてはクーリング・オフ(無条件解約)という制度があります。
一方で、通信販売にはそのような制度はありません。
ですが、申し込みの撤回や自己都合による返品の可否についてホームページ等に記述していない場合には、一定期間内である限り、利用者側から契約をなかったことにできます。
言い換えれば、広告に「解約不可」、「返品不能」などと記述していれば、基本的に解除を防ぐことができるようになります。
仮に、このような広告をしていなかったために返品を受けつける場合であっても、送料など返品に必要な費用はお客様の負担となります。
一部業者が返品手数料を負担しているケースもありますが、これはその業者がサービスとして行っていることになります。規約等で定めていなければ基本的に送料の負担をする必要はありません。
・消費者との関わり方
消費者相手のビジネスの場合、大きく2つの関わり方があります。
一つは、旅館等の宿泊業、レストラン、料亭等の飲食業、各種学校など、サービスを提供することに重点を置いたビジネスです。
もう一つは、各種の物品を販売する物品提供に重点を置いたビジネスです。
解約という観点から2つのビジネスを分析するとそれぞれ特徴があることがわかります。
サービス提供型であれば、予約を無視されたような場合、大きな損害が生じることが多いと考えられます。
一方、物品提供型の場合には、キャンセルがあっても、商品を引き続き販売することが可能であることが多く、解約に起因した損害が生じることは考えにくいといえます。
したがって、2つのビジネスの違いに分けて検討する必要があります。
■ポイント2~サービス提供型の場合
サービス提供型といっても、飲食業など単発型のものと、各種学校などの継続提供形に分かれます。また、他の人に提供できなくなるという排他性による分類も考えられます。
・単発型
飲食業や宿泊業などのサービス業の場合、予約されていたにもかかわらずキャンセルされた場合、他の利用者に提供できなくなり、損害が発生するおそれがあります。特に直前のキャンセルや無断キャンセルではその可能性が高くなります。
まず、「予約」という言葉について整理しておきます。
法律上の用語としては、「将来、本契約を結ぶことを約する契約」のことをいいます。
つまり、本来の契約はまだ結ばれていません。
したがって、予約に基づいた権利をもっている人が、それを行使しない限り、本来の権利や義務は発生しないことになります。
そうだとすると、予約を入れただけのお客様にキャンセルされたとしても、なにも言えないようにも思えます。
ですが、当事者の意思表示として、「○時に○名で予約をお願いします。」、「お待ちしております。」というやり取りがされた場合、約束の日時にサービスの提供を行うことが必要となり、お客様から見るとサービスを受けられる期待が生じることから、目的の債権、債務が具体的に生じたといえ、「予約」と呼ばれてはいるものの、本契約そのものと考えられます。
したがって、一方的にキャンセルされた場合、相応の請求をしていくことが可能です。
では、いくらくらい請求できるのでしょうか。
それは原則として、一般的に生じる損害の範囲内ということになります。
必ずしも金額を明記しておかなければ請求できないというわけではありません。
ですが、金額や計算方法が明らかにされていないと、トラブルのもとになります。
また、あらかじめ合理的な算定方法を定めておくことでお客様に理由を説明することも容易になります。
キャンセル料についてあらかじめ定めておくことの意味がここにあります。
あらかじめ明確な規定があれば任意に支払ってもらえることも期待しやすくなるのです。
定めを設ける際には、その事業者の当該業務について生じる「平均的な損害額」になることが必要です(業界の平均ということではありません。)。
これを超えた場合、その規定全体が無効になるわけではなく、オーバーしたところだけが無効とされます。
そのため、少し多めに見積もっておこうと考えてしまうかもしれませんが、相手に納得してもらうことでトラブルを避ける意味合いもありますから、合理的な範囲内に留めることが大切です。
具体的な算定方法ですが、「本来受け取れたはずの金額ー(本来かかったはずの費用+再販による利益)」となると考えられます。
そこで、平均値を出すためには、「本来受け取れたはずの金額×粗利率×非再販率」が妥当と考えられます(京都地裁平成26年8月7日判決参考)。
サービスの金額が限定されているような場合には、具体的に金額を定める方法もありますが、旅行業などでの一般的な定め方としては、パーセンテージで表すことが多いといえます。金額がある程度決まっている場合には、パーセント表記と併せて「最高限度額」として具体的な金額を定めることも安心感を与えます。
いずれにしても、利用者にわかりやすい表示にすることがトラブルを防ぐ上で重要なことです。
※上記裁判例のケースは結婚式場の事案で、確定的な金額ではなく見積額の平均値を出さなければならない場合でした。計算式は上記事案に基づいたもので、他のケースでは異なったものになる可能性も否定できません。例えば、営業努力を怠り、再販率が極めて小さい事案では何らかの手当が必要であると指摘されています。
・継続提供型
一定の期間に渡ってサービスを提供するもののうち、一定の要件を満たすものについては金額の上限が定められています。
サービスの提供前では、学習塾(1万1,000円)、語学教室(1万5,000円)、パソコン教室(1万5,000円)、美容医療(2万円)、エステティックサロン(2万円)、家庭教師(2万円)、結婚相手紹介業(3万円)となっています。
※サービス開始後はさらに制限されます。それぞれ5万円を上回るものが対象です。また、エステと美容医療については、期間が1ヶ月を超えるもの、その他は2ヶ月を超えるものが対象です。
・排他的でないサービス
携帯電話等の通信サービスや動画配信等のWEBサービスなどでは、キャンセルされたとしても、それにより再販売が可能になるという関係にありません。
そのため、通常は損害額として、「残りの契約期間×1ヶ月あたりの利用料×粗利率」として計算するのが妥当と考えられます。
■ポイント3~物品提供型の場合
・キャンセル料
通信販売など物品を提供するタイプである場合、通常は再販売が可能ですから、キャンセルに起因した損害というのは認められにくいといえます。
もっとも、特注品のような他者に再販することが不可能な場合であれば損害となりえます。
・返品特約
前記のように、通信販売にはクーリング・オフは存在しません。
よく似た制度として、受領した日から8日以内であれば、お客様の側から白紙撤回することが認められています。
これには例外があり、広告内容に返品や解約ができない旨を明記したときは、この権利を否定することができます。
したがって、キャンセルされたら困る場合には、料金を設定するのではなく、解約自体を制限することが重要と考えられます。
その際の具体的な記載方法としては、解約自体を禁止したければ「解約不可」、商品価値の減少を気にするのであれば「返品不可」や「開封後の返品不可」などとすることが考えられます。
この表示の仕方ですが、非常に小さい文字で記載したり、わかりにくい箇所に記載したりすると広告する意味がありませんから、誰にでもわかりやすく認識できるように記載する必要があります(通信販売における返品特約の表示についてのガイドライン(消費者庁))。不適切だと判断されると効力が否定されてしまいますから注意が必要です。
(自己都合による)返送にかかる費用については明示していなくてもお客様の負担となりますが、トラブルを防ぐためには記述しておいたほうが望ましいといえます。
■裁判例
・挙式披露宴に関するキャンセル料事案(京都地裁平成26年8月7日判決)
消費者団体Xが婚礼、披露宴に関する事業を展開するY社を相手方として、挙式披露宴実施契約に付随するキャンセル料規定が損害額の平均を上回り違法であるとして、出訴したケース。
特に問題となったのは、申込金が規制対象となるかという点、平均的損害の中に解約に起因する逸失利益が含まれるかという点です。
まず前者については、申込金を特別扱いする理由はなく規制の対象になるとしました。
後者については、一般的な損害賠償の請求は、通常生じる損害について行うことができるが、ここには逸失利益が含まれ、この場合と区別する理由はないとしました。
■まとめ
・トラブルを防ぐためにはキャンセル料を定めておくことが重要です。
・上限額が定められており、具体的な業務の「平均的な損害」の範囲でなければなりません。
・美容医療など一部の業務については具体的な金額による規制もあります。
・通信販売にはクーリングオフはありませんが、一定期間内であれば解約可能です。ただし、広告に記載することで禁止することができます。その際はわかりやすく書かなければなりません。
・物品販売は再販がしやすいことから、キャンセル料を規定しても無効とされやすいといえます。そのため、解約や返品自体を禁止する方法も検討します。