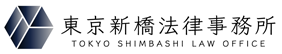〇 はじめに
瑕疵修補請求権とは、その文言通り読むと“相手方に対して瑕疵を修補するよう請求する権利”ということになります。難しい用語がいくつかありますが、「瑕疵(かし)」とは“契約対象物に生じたきず”と、「修補」とは“不完全な点を治すこと”と、イメージして捉えていただければと思います。そうすると、瑕疵修補請求権とは“相手方に対して契約の対象物に生じているきずを治すよう請求する権利”ということになります。
だいたいのイメージをもっていただいた上で、これから、瑕疵修補請求権について具体的な説明をしていきたいと思いますが、以下の様な過程を踏みながら、説明を加えていきたいと思います。まず、瑕疵修補請求権を検討する前提として、どのような場合が法律上の「瑕疵」に該当するのかを理解する必要があります。そのため、まずは、①「瑕疵」の意義について検討をしていきたいと思います。その上で、②瑕疵修補請求権が問題となる場面について検討を重ねていきたいと思います。そしてさいごに、請負契約の瑕疵修補請求権を検討する際に問題となる、③瑕疵修補請求権に代わる損害賠償請求について説明を加えたいと思います。
それでは、以下でさらに細かい説明をしていきたいと思います。
①「瑕疵」の意義について
瑕疵修補請求権を理解するためには、その前提として、法律上の「瑕疵」とはいったい何なのかということを理解する必要があります。
その点について、判例は「瑕疵」とは「個々の契約の趣旨に照らして、目的物が通常有すべき品質・性能を欠いていること」であると示しています(最高裁昭和56年9月8日判決)。つまり裁判所は、取引において一般的に要求される水準で「通常有すべき品質・性能を欠いている」場合(これを客観的瑕疵といいます)にとどまらず、契約の際に契約当事者の間で予定されていた性質を欠いていることも「瑕疵」に該当する(これを主観的瑕疵といいます)と判断しているのです。
ここまで、“「瑕疵」とは客観的瑕疵のみならず主観的瑕疵も含まれる”という内容を説明してきました。客観的瑕疵とは、誰が見てもわかる欠陥であるのでわかりやすいと思うのですが、一方で主観的瑕疵とはなかなかイメージしにくいのではないのでしょうか。
そこで、主観的瑕疵が問題となった具体例として、最高裁平成15年10月10日判決の事情がわかりやすいので、以下で挙げたいと思います。
この事案では、建物を建築することについて請負契約が結ばれていたのですが、その建築を行う際には、より耐震強度を高めたいという注文者側の希望に沿う形で、300mm×300mmの鉄骨を建材として用いて建設をするという事を当事者の間で決めていました。しかしながら、建設を請け負った者(請負人)は、250mm×250mmの鉄骨を用いて建設をしてしまいました。その点について、裁判所は「瑕疵」があると認定を行ったのです。
これは、仮に、250mm×250mmの鉄骨を用いた建物でも全然耐震性に問題は生じず、取引において一般的に要求される水準で「通常有すべき品質・性能を欠いている」とまではいえない様であったとしても、請負契約の際に契約当事者の間で予定されていた性質、つまり「建築を行う際には30mm×300mmの鉄骨を建材として用いて建設をする」という決まり事を破っていることについては「瑕疵」があるといえるので、法律上の「瑕疵」が認められるといえるということなのです。
〇 瑕疵修補請求権が問題となる場面について
瑕疵修補請求権が問題となる場面は、大きく2点あります。1つ目は売買契約(民法555条)の対象物となる売買目的物に瑕疵が生じていた場合、2つ目は請負契約(民法632条)の対象となっている仕事の完成物に瑕疵が生じていた場合です。前者よりも後者の方が、よく論じられることが多いので、ここでも後者を中心に解説していきたいと思います。
① 売買契約における瑕疵修補請求権
売買契約おける瑕疵修補請求権については、売買契約における瑕疵担保責任(民法570条)の一環として、売買目的物の瑕疵を修補するよう請求できるかという点で、明文化された規定がないため問題となっています。学問上は大きく問題とされている点ですが、ここでは踏み込みません。
実務上では、新築住宅の売買の場合について、住宅の品質確保の促進に関する法律という法律により、特例で瑕疵修補請求が認められています(同法95条1項、民法634条1項)。
② 請負契約における瑕疵修補請求権
請負契約とは特定の仕事の完成を内容とする契約です(民法634条参照)。請負契約における瑕疵修補請求権とは、請負契約によって完成した仕事の成果物に「瑕疵」がある場合、その「瑕疵」を補填するために行う修補請求及びそれに代わる損害賠償請求のことをいいます。太字で記載をしましたが、一般的な立場に立つと、請負契約に基づく瑕疵修補責任を追及するためには、少なくとも仕事が完成していることが前提となっているという点は重要です(仕事完成前の問題は、債務不履行として問題となると考えられています)。どの段階が「仕事の完成」に該当するかについても、いくつかの争いがありますが、公示が予定されていた最後の工程まで一応終了した時点で「完成」と考える立場が有力であるといえます(この立場を最終工程説といいます。東京高裁昭和36年12月20日判決参照)。
売買契約における瑕疵修補請求権とは異なり、請負契約における瑕疵修補請求権は民法の条文に明記されています。
634条1項 仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でない場合において、その修補に過大の費用を要するときは、この限りではない。
注文者として、請負人へ請負契約に基づく瑕疵修補請求を求める場合には、①請負契約が成立していること、②請負契約に基づく仕事が完成していること、③目的物に「瑕疵」があることの3点を主張していくことになります。
この請求に対して、相手方(請負人)からは「瑕疵が重要でな」く、また修補の為に「過大の費用を要する」場合は、瑕疵修補請求は認められないとする民法634条1項ただし書に該当するといった反論がなされることになります。
③ 瑕疵修補請求権と債権回収の関係 瑕疵修補請求権に代わる損害賠償請求について
ここまで、瑕疵修補請求権が問題となる場面について、とくに請負契約に基づく瑕疵修補請求権について中心に、その内容を説明してきました。しかしながら、実際のところ請負契約に基づく瑕疵修補請求権(634条1項)が、債権回収の手段として直接使用されるような場面はほとんどないといえます。
請負契約の仕事の完成物に瑕疵がある場合、多くの場合は瑕疵修補請求権に代わる損害賠償請求を行うことになります。瑕疵修補請求権に代わる損害賠償請求については634条2項に規定があります。
634条2項 注文者は、瑕疵の修補に変えて、又はその修補とともに、損害賠償の請求をすることができる。この場合においては、第533条の規定を準用する。
634条の「修補に代えて」とは、注文者は不完全な仕事をした請負人に対して修補を請求するのみならず、選択肢として損害賠償を請求することも認められるという意味であるとされています。
実際に裁判所は、請負人の再工事により瑕疵の修補が可能である場合にも、修補を請求せずに直ちに修補に代わる損害の賠償を請求することができると判断しています(最高裁昭和54年3月20日判決)。
債権者(注文者)としては、不完全な仕事を行った請負人に対して、「もう一度工事して、不完全な部分を修理してください」と請求することもできますが、「もう同じ相手方に工事してもらいたくない」と感じる方もいらっしゃると思いますし、場合によっては、いくら催告しても請負人が頑なに修補に応じない、といったことも十分考えられます。そのため、より確実な損害の補填・債権の回収のために、瑕疵修補請求権に代わる損害賠償請求は有効な手段であると考えられます。
〇 まとめ
以上に指摘した様な契約の目的物に問題点がある場合には、瑕疵修補請求権が行使できる場合があります。また、瑕疵修補請求権そのものの請求ではなく、それに代わる損害賠償請求という手段が有効であるということも指摘しました。しかしながら、前述の通り、請求ができる期間が限定されている点など、それらの請求が認められるためにはいくつかのハードルがあるといえます。まずは、専門家である弁護士に相談し、適切な請求をするためにはどのような方法をとるべきかといったアドバイスを受けることが重要となるといえます。
※ 法律用語集へ戻る