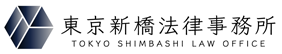違約金とは、当事者間で交わした契約を当事者の一方が違反したりした場合に、発生した損害を賠償する代わりに設定する金銭のことを言います。
契約の不履行に基づく損害が発生した場合は、民法上当然に損害賠償請求ができるとされています。(民法415条)もっとも、この場合どれほどの額が損害として発生したのかについての計算と、その発生した損害のうち、相手方の過失割合はいくらなのかという複雑な計算についても、損害賠償請求を主張する側が立証する必要があるため、大変な労力となります。それに対し、あらかじめ損害賠償の予定額としての違約金を設定していれば、このような詳細な計算や立証が必要でなくなるため、契約違反時の対応が極めてスムーズとなります。もっとも、どのような額を違約金として設定するかについては相場観を要するものですから、債権回収に詳しい弁護士に相談することが必要とされます。
違約金の請求が問題になる身近な3つの事例
違約金の取り決めは、不動産の売買やエステのサービス契約など、色々な分野で行われています。身近で特に違約金の請求が問題になることが多いのは、次のような3つのケースです。
不動産売買などの不動産に関する契約
不動産売買などの不動産に関する契約においては、ほとんどの場合に違約金の条項が存在します。重要事項説明書にも違約金についての違約金について書かれていることが基本です。
サービスや売買の契約
不動産以外の売買契約でも、よく違約金の取り決めが行われています。たとえば、高額のエステのコースを契約したさいの違約金や、通信サービスを短い期間で解約した場合の違約金などが見受けられます。このように、一般的なサービスの契約に違約金の条項を置いていることも、よくあることです。
旅行や宿泊施設の契約
身近な契約の中の違約金といえば、旅行や宿泊施設の違約金もお馴染みです。ホテルや旅館などは特に、キャンセル日によっては違約金の請求がなされることがあります。また、団体旅行(パックツアーなど)も、キャンセルによって違約金が発生することがあります。
違約金を定めていても制限されるケースがある
このように、違約金は身近な契約の中で使われています。基本的に違約金の契約条項があれば、記載に添った効力が発生します。しかし、違約金さえ定めていれば必ず対象になるわけではありません。中には、違約金の請求が制限されるケースがあるのです。
違約金が制限される代表的なケースが、「公序良俗に反する場合」です。
違約金の内容が公序良俗に反する場合や、違約金の額が極めて過大で場合などは、契約で違約金を定めても制限されるケースに該当します。
契約において公序良俗に反するというのは、倫理や正義、道徳などに反していることを意味します。たとえば、愛人契約や殺人契約などが公序良俗に反する契約にあたります。
もう1つの代表的なケースが「不動産売買で宅建業者が売主になる場合」です。
不動産売買で宅建業者が売主になる場合は、損害賠償の予定額と違約金を合わせた金額が売買代金の10分の2を超えることができないこと、そして10分の2を超えてしまった部分については無効になることが、宅建業法38条によって定められています。
損害賠償の予定額としての違約金を設定した場合に超過分は請求可能か
損害賠償の予定額として違約金を設定した場合、違約金を遥かに超える損害額が出た時はどうするのかが問題になります。損害賠償の予定額として違約金を定めた場合は、基本的に設定した違約金の額での請求になります。
ただし、高額のお金が動く契約では特に、違約金を超えるような大きな損害が発生したら、損害について相手方に請求したいと考えるのではないでしょうか。
実務では、違約金を超える部分の損害賠償請求について定めた条項を置いて、請求可能にすることが行われています。
この条項を契約書に記載することにより、大きな損害が発生した時のリスクヘッジが可能です。
後のトラブルを防ぐためには、違約金の条項を置いた契約書のリーガルチェックを徹底することが重要です。
※ 法律用語集へ戻る