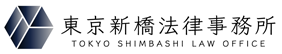目次
はじめに
会社の従業員が新しく会社を設立して独立することになり、「おめでとう!」と言って見送ったのも束の間。いつの間にか会社からもう一人辞め、二人辞め…なぜか重要な人材がどんどん辞めていきます。後になって知ったところによると、辞めた皆は独立したあいつの会社で働き始めたという!貴重な人材を取られてしまった!なんということだ!
こういった従業員の引き抜き行為は、とりわけ個々の人材の重要性の高いIT業界で近年多く見られます。
大事な人材を引き抜かれた会社の側はたまったものではありません。出て行ってしまった人材が会社を引っ張っていたエースであれば、会社の業務が回らなくなってしまう可能性すらあるので、なおのことです。
さらに、自社で身につけた技術を競合他社での業務で使われてしまう危険性もあります。
では、優秀な人材を引き抜かれた場合、会社は引き抜いた相手の会社に対して損害賠償請求できるのでしょうか?また、出て行ってしまった従業員本人に対してはどうでしょうか?
今回の記事では、従業員引き抜きに関してどういった場合に誰に対して損害賠償請求ができるのかを説明していきます。
引き抜かれた従業員本人に対する損害賠償請求はできる?
辞めて行った従業員本人に対しては、会社は原則として損害賠償請求はできません。
なぜなら、憲法によって国民には職業選択の自由が認められていますが、転職の自由も当然そこに含まれていると考えられるからです。民法でも、従業員は2週間前に通告すれば会社を辞めることができると定められています(民法672条1項参照)。
では、競合他社に転職して営業の秘密をバラされると困るなどといった理由で、従業員に「少なくとも、会社を辞めてから○年間は競合他社に転職しません(競合する会社を設立しません)。」といった内容の誓約書を提出させていた場合はどうなのでしょうか?この契約を破ったとして、損害賠償を請求できるのでしょうか?
使用者の利益をむやみに害してはいけないという従業員の義務と、転職の自由とがせめぎ合う場面で、どうバランスを取るべきなのでしょう。
こういった事例についての最高裁判所の判決はまだありませんが、「フォセコ・ジャパン・リミテッド事件」という奈良地裁の有名な判決があります。
この判決では、上述のような競業禁止の特約が「合理的な範囲」を超えてしまったら、その特約は無効になると判断されました。「合理的な範囲」に入るかどうかは制限の年数や業種など様々な事情の総合考慮によって判断されるため、個別の事例において当事者が「これは合理的な範囲だ!」と明確に判断するのは難しいでしょう。
引き抜かれる会社の側としては念のため、基本的には転職を制限する契約は無効になるものと考えておいたほうが良さそうです。
ちなみに上のフォセコ・ジャパン・リミテッド事件では、辞めた従業員が会社にとって重要な技術上の秘密を握っていたことや、競業禁止の期間が2年間と短かったことなどが考慮されて、結局、原告の請求が認められ、元従業員は事業活動を停止すべしという判決が下されました。
退職後に競業した場合の退職金の扱いは?
また、損害賠償は請求できなくとも、退職後の競業が就業規則違反にあたるとして、退職金の一部または全部の支払を拒否することができる可能性があります。
これについても、退職金の減額割合や、退職に至るまでの経緯、会社の被った損害の程度など様々な事情が考慮され、判断されることになります。
引き抜いた他社に対する損害賠償請求
次に、最初から会社と全く関係を持っていない者、たとえば競合他社からのヘッドハンティング等によって従業員が辞めてしまった場合、引き抜いた側の会社に対しては損害賠償を請求できるでしょうか。
答えは、ノーです。
従業員として働く人々は、より良い労働条件を提示してくれる会社で働きたいと思うのが当然ですし、また機会さえあればそういった会社へ転職する自由を持ち合わせるのは上述の通りです。
そして、そういった自由があるのですから、会社が優秀な人材に来てもらうために積極的に働きかけをすることも当然に認められます。
人材獲得についても自由競争を前提とする以上、優秀な人材を獲得するためには、会社側が高い報酬や充実した福利厚生などを提示して積極的に勧誘し、又は社内に止まってもらうように説得しなければならないのです。
しかし、何事にも限度というものはあります。
ラクソン事件と呼ばれる裁判例は、社運を賭けた一大プロジェクトを任されていた社員が、競合他社との綿密な計画と話合いの下、部下20人超を引き抜いたという事案でした。この引き抜きを行った社員と競合他社とは、「極めて背信的」な方法で引き抜きを行ったとして、引き抜かれた側の会社に対して共同不法行為の責任を負い、損害賠償を支払わなければならないと判断されました。
自由競争の範囲を超えた不当な引き抜きは不法行為に当りうるということは、心に留めておきましょう。
自社の取締役による引き抜き
会社で現在まさに取締役をやっている者が、会社を辞めて自分の会社を立ち上げよう、若しくは競合他社へと転職しようと画策しているときに、「これから自分と一緒に別の会社で働かないか」と部下である従業員を勧誘した場合はどうでしょうか。その勧誘の結果、従業員が辞めてしまったら、会社はその取締役に損害賠償請求できるのでしょうか?
取締役は会社に対していくつかの義務を負うことが会社法の中で定められていますが、その中の「忠実義務」が従業員引き抜きとの関係で重要になってきます。
ここでいう忠実義務とは、会社と取締役の利害が対立する状況になったとしても、取締役は私利を図らずに会社の利益を守るよう行動すべし、という義務です。
会社から従業員を引き抜いて別の会社へ勧誘するとなると、明らかに会社の利益と取締役の利益が対立していますし、そのような状況下で取締役は会社の利益を犠牲にして自分の利益を図っているように思われます。従業員引き抜きは忠実義務に反したことになるのでしょうか。
これについては、取締役が在任中に勧誘行為を行ったら、当然全てが忠実義務違反になるとする見解と、事情によっては忠実義務違反にならない場合もあるとする見解とに分かれています。
最高裁の裁判例はまだありませんが、下級審の裁判例はたくさんあり、そのうちの多くは、業種や引き抜かれた従業員の人数、その引き抜き行為が会社に与える影響の大きさ、どのような方法で引き抜きが行われたのかといった諸々の事情を総合的に考慮して、忠実義務違反にあたるかどうかを判断しています。
つまり下級審の裁判例の多くは、事情によっては忠実義務違反にならない場合もあるとする見解に寄っているのです。
会社の規模や、取締役が退任した事情、取締役と引き抜かれる従業員との関係(自ら育成した部下かどうか)などは様々であるため、一律に忠実義務違反にしてしまうと納得できない結果を生みかねない、というのがその理由だと考えられます。
入社当時から子飼いにして長年熱心に育成してきた部下を一人だけ、自分の会社に引き抜いただけで忠実義務違反になってしまうというのは、一般人の感覚としてもおかしいと思いますものね。
ちなみに、取締役ではない一般の従業員が、自分がこれから設立もしくは転職する会社に他の従業員を勧誘する場合については、ほとんどの場合は違法にはなりません。
このような従業員は取締役と違って会社法の忠実義務を負っていないため、引き抜きが社会的に許されないような方法で行われた場合(会社に大ダメージを与えようとする目的で大量に従業員を引き抜く等。前出のラクソン事件を参照してください。)にのみ、引き抜き行為は違法となるのです。
さらに、比較的新しい平成26年の東京地裁の裁判例は、従業員(取締役ではない)による派遣労働者の引き抜きについては「著しく背信的」な方法で行われた場合にのみ違法となるとしました。
派遣労働者は正社員に比べて地位が不安定であるがゆえに転職へのインセンティブはより強いため、違法とされる引き抜きの範囲は一層狭まっているということです。
すでに辞めた元・自社取締役による引き抜き
取締役を退任して会社を辞めてしまえば、元・取締役は当然、上述のような取締役の忠実義務からは解放されます。
そのため、取締役として勤務している期間中に何も働き掛けをしておらず、退任してから従業員の勧誘を始めたのであれば、上で説明した競合他社からのヘッドハンティングの場合と同様、引き抜きに違法性は認められません。
もちろん競合他社の引き抜きの場合と同様、そのやり方があまりにひどく、背信的であると認められた場合には、違法な引き抜きと評価される可能性はあります。
これに関して2005年に話題になったのが、大手のモデル事務所「クリエートジャパンエージェンシー」の元取締役らが、自分たちで新しく設立した会社「フラッグスファイブプロモーション」へと、前者のモデル72人を引き抜いた事件の判決です。元取締役らは、一定期間にわたって集中し、また退職後かなり長い期間にわたって、クリエートジャパンエージェンシーを批判しながら100人超のモデルを電話などで勧誘していたということで、このような引き抜き行為は「著しく社会的相当性を欠く」として不法行為に当ると判断されました。
競業避止義務違反を理由とした損害賠償請求
また、引き抜き行為そのものではなく前出の競業避止義務違反を理由にして、会社からの損害賠償請求が認められる可能性はあります。
東京学習協力会事件という東京地裁平成2年4月17日の裁判例では、進学塾の講師2名が同じ塾で働く他の講師12名を勧誘して元勤務先の至近距離で学習塾を新設し、同時に生徒の名簿を利用して自分の塾に鞍替えするよう呼びかけたという事案で、競業避止義務を定めた就業規則違反を直接の理由として学習塾側の損害賠償請求を認めました。
一方で、競業避止義務を定める特約や就業規則がなければ、退職後の取締役や従業員の競業は不法行為にならないとした池本自動車商会事件(大阪地裁平成8年2月26日)の裁判例もあります。
会社の側としては、裁判になった場合に引き抜き行為の違法性を認めてもらいやすくするという観点からも、退職後の競業避止義務については就業規則で定めておいたほうが良いかもしれません。
請求できる損害賠償の額は?
引き抜き行為が違法もしくは債務不履行に当ると判断されたとして、引き抜かれた会社は一体どの範囲で損害賠償請求が認められるのでしょうか。
引き抜き行為による会社の損失額は、立証がとても困難です。
引き抜き後に会社の売り上げが下がったという事実があるとしても、景気の悪化や他の従業員のミスなど他の要因はいくらでも考えられるため、引き抜きとの因果関係をハッキリすることはほぼ不可能と言って良いでしょう。
また、引き抜き行為をした会社が引き抜き後に売り上げが上がったとしても、その上昇分を損害と考えることも、同じ理由で難しいものがあります。
さらに、引き抜きを行ったのが取締役である場合、その報酬を損害賠償請求で没収できないかと考える人もいるかもしれません。
しかし、忠実義務に違反した引き抜きを行ったからと言って、取締役としての報酬が不当利得になるとは限らないと判断した東京高裁平成元年10月26日の裁判例もあるため、これもあまり期待できないでしょう。
取締役としての業務をほとんど行わずに引き抜きの準備ばかりやっていた場合や、極端に成果が悪いといった場合等に限っては、もしかしたら不当利得として報酬を返してもらえるかもしれません。
裁判例全体の傾向として、引き抜き行為との相当因果関係が認められて損害賠償請求が認容されている会社の損害は、引き抜かれた人員の育成にかかった費用や、従業員引き抜きと同時に奪われた得意先に対する売り上げの減少分、といった程度にしかすぎません。
せっかく引き抜き行為自体は違法であると判断されても、思うような賠償額は獲得できないというのが実情です(前出の平成元年10月26日の判決では、引き抜き行為後に新しい人材を採用・教育して会社が元の状態に戻るまでに必要とされる期間の逸失利益を損害として認めました。中にはこのような裁判例もあります)。
まとめ
従業員引き抜きを理由とした損害賠償請求が認められるかどうかは、結局、個々の場合について多くの事情を総合考慮することによって判断されるところが大きいので、裁判で判決が出る前に当事者が判断するのは難しい、というのが正直なところです。
確実に言えることは、引き抜かれた従業員が会社にとって重要な人材であったことや、引き抜きのやり方が悪質であること、会社への影響が大きいことなどが、損害賠償請求を認めさせる方向へ働くファクターであるということです。
会社にとって迷惑な引き抜き行為があった場合は、早めに弁護士に相談した上で、こうした事実を立証するための証拠を集めるようにしましょう。
このような損害賠償請求などの債権の回収についてのご相談もお気軽にご連絡ください。