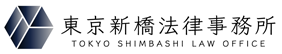目次
■はじめに
■ポイント1~同時履行の抗弁権とは
■ポイント2~認められるための要件
■ポイント3~具体的な効果
■ポイント4~代表的な問題
■ポイント5~その他の問題
■まとめ
■はじめに
商売などビジネスに限ったことではありませんが、なんらかの取引を行う場合、相手との信頼関係が重要となります。
しかし、必ずしも安心して取引できるとは限りません。
初めて知り合った人物だけではなく、昔から知っている人物との間であったとしてもトラブルは起こります。
そのトラブルの内容もいろいろです。
例えば、取引があったかなかったか、あったとしてその内容がいかなるものであったかという成立時の問題があります。
この問題への対処方法としては、契約書を作るなど物証を残す方法が考えられます。
それが偽造されるおそれもあるため、重要な取引の場合には第三者に立ち会ってもらう方法を併用することもあります(不動産取引が代表例です。)。
事前に対策を立てやすい問題といえます。
これに対し、成立したことを前提として、様々な理由をつけて支払ってもらえなかったり、一部しか応じてもらえなかったりといった履行時の問題もあります。
事前に対策を立てることが難しく、個別の事案に応じて柔軟に対応しなくてはならない為、やっかいな問題といえます。
そこで、取引の基本的な理念である公平性の原則を前提にした、「同時履行の抗弁権」という制度が存在します。
ここでは、この制度について基本的な内容を解説していきます。
ポイント1~同時履行の抗弁権とは
この制度は、相手から義務を果たすよう求められたときに、相手にも対応する義務を果たすことを求めるためのものです。
契約のうち、お互いに対価的な義務を生じさせるものを双務契約といいます。
つまり、お互いに相手に対して、お金や物、サービスを提供する義務を果たさなければいけないもののことです。
具体的に生じた義務を果たす場合、それが相手方の義務の実行と関係なく行わなければならないとすると問題が起こります。
例えば、商品を届ける義務があるときに、相手の義務であるお金の支払の有無と無関係に義務を果たさなければいけないとしたら公平とはいえません。
それは一般的にお互いの意思にも一致しないはずです。
また、経済活動における重要な要素である簡易かつ迅速な取引という要請にも反します。
そのため、このような関係にある場合には、一緒に義務を果たすことが重要です。
これを実現するために法制化したのが本件の「同時履行の抗弁権」という制度であります。
自分が義務を果たさなくても、相手も果たさない限り違法とはされないのです。
例えば、商品をもらっていないのに代金を請求された場合、商品をもらうまで支払わないと主張して拒否できるのです。
ポイント2~認められるための要件
一つの契約によって生じた対立する債務があること
贈与のように一方的に義務を負う場合には問題になりません。
債権が譲渡されたり、債務引受があったりして当事者に変更があった場合が問題となりますが、このようなことがあった場合でも、新しい当事者に対して主張することができます。同じ債務であることに変わりはないからです。
例えば、AがBにパソコンを販売した場合に、Aが当該売掛債権をCに売却したときは、Cから請求を受けたBは、パソコンを受け取るまで支払わないと主張できます。
互いに弁済期にあること
どちらか一方が、まず義務を果たすべきこととなっているときは認められません。
例えば、9月1日にAがBにパソコンを販売した場合、代金の支払いは9月末日と定めていたときは、販売した当日にBからパソコンを要求されたAは、原則としてこれを拒否できません。
問題となるのは、義務を果たしていない間に相手の弁済期も到来した場合です。
相手の期限も到来している以上、抗弁権を認めてもいいように思えますが、一方で、履行しなかった人が悪いわけですから、否定すべきようにも思えます。
結論としては、このような場合にも認められると考えられています。
例えば、前記のケースで、パソコンを渡すことなく10月になってしまった場合に、Bから要求されたAは、代金をもらえるまで拒否すると主張できます。
遅れた人はそれによって生じた損害を補償する責任があり、これを免れるわけではありません。
つまり、遅れてしまった責任と、公平の見地から一緒に義務を果たすこととは、別の問題と捉えるわけです。
相手が自分の義務を果たさずに請求してきたこと
自分がなすべきことをしないで一方的に要求する、これがおかしいというのが本制度の根底にある考え方だからです。
問題なのは一部を実行してきた場合です。
このような場合には、それぞれのケースに応じて判断していくしかありません。
基本的な指針は、「公平性」があるかという点にあります。
可分債務であることが前提ですが、基本的に残った相手の義務に相当する部分だけ拒否できます。
ですが、残った相手の義務が些細なものであるときは、一切拒否できないと考えられています。
反対に、残った相手の義務が重要なものであるときは、全体について拒絶できると考えられます。
ポイント3~具体的な効果
積極的に用いた場合
権利の実現は、最終的には訴訟の場で認められてはじめて達成されます。
本制度の権利も同様であり、訴訟で認められると、相手方に対し、原告が義務を果たすのと引換えに、その義務を果たすべき旨の判決が下されます。
その後、自分が義務を果たしたことを証明して強制執行を行っていくこととなります。
何もしていない場合
積極的に用いない場合でも、一定の効果が認められています。
自分が義務を履行しない限り、相手方も対応する義務の履行を拒否できるわけですから、損害の補償を求めたり、契約を解消したりするためには、目的物の提供等をしていかなければなりません。
つまり、何もしなければ遅滞の責任を問えないという効果があります。
相殺を封じる効果
お互いに負担する同種の債務は、期限が共に来ている場合、相手方に対する一方的な意思表示によって対当額の範囲で消滅させることができます。
ですが、その性質から一方的に消滅させることが好ましくないものもあります。
抗弁権が存在するものがその典型例です。
もしこのような場合にも一方的な消滅を認めた場合、相手方の状況を不利にしてしまうおそれがあるからです。
例えば、AがBから30万円を借りていた場合に、その後AがBにパソコンを30万円で売却したとき、Aはパソコンを提供することなく相殺することはできません。
もし認めてしまうと、Bは債権を失った上、パソコンも受け取れなくなるおそれがあるからです。したがって、Bの側から相殺することは許されます。
ポイント4~代表的な問題
領収書の発行
代金や商品を相手に渡したとしても、それが証明できないと困ります。
一般的に、義務を果たしたことを証明するためには、内容を明示した相手方の署名や捺印の入った書面が用いられます。
そのため、受け取ったことを示す書面の交付を求めることができ、それに応じない限り代金の支払い等を拒否できるとされています。
契約書等の返還
債権の存在を示す文書があるときは、義務を完全に果たした人は、その返還を要求できます。
ですが、前記のケースとは違い、返還されないとしても弁済を拒否できないとされています。
受け取ったことの証明には領収書で十分ですし、返還を必須としてしまいますと、紛失してしまっている場合に不都合だからです。
契約から直接生じたものでない場合
この権利が認められるのは、本来、一つの契約によって発生した対立する債務が存在する場合です。
ですが、この制度の目的は、公平性の確保や、簡易かつ迅速という経済取引の要請を実現することにあり、契約者の一般的な意思にも一致させるためです。
そうであれば、このような考え方が妥当する他の問題にも適用を認めるべきことになります。
具体的には、契約が何らかの理由によってなくなった場合、互いに商品や代金を受け取っているときは、それらを手元においておく正当な理由がないわけですから、返さなければなりません。そこで、この返還義務についてもこの制度が利用できることになっています。
担保権消滅とその手続
抵当権や根抵当権などが設定され登記されている場合、抹消手続きをしてもらわないと困ることになります。
そこで、返済するのと引換えに手続きをとってもらえるのかという問題があります。
しかし、このような場合には、返済を先にする必要があるとされています。
登記手続等の準備を行うことは負担が大きく、公平とはいえないからです。
ポイント5~その他の問題
留置権との違い
履行の拒否を正当化する制度という点では共通しています。
しかし、一方は債権であり、もう一方は物権であることから根本的に性質が異なります。
両者の違いはこの点が決定的といえます。
物権である以上「物」のみが対象となるのに対し、本件制度は債権である以上、給付内容を問わず適用されます。
また、債権と異なり物権であることから第三者に主張することができます。
債権と異なり不可分性があるという違いもあります。
それぞれの性質を考慮して、適切な権利を選択していくことが重要といえます。
不安の抗弁
双方が一緒に義務を果たす約束であればそれほど問題は複雑となりません。
しかし、実際の取引においては、一方は後で義務を果たせばよいことになっていることが少なくありません。
そのような場合に、後で義務を果たすべき相手方について、財産状況が悪くなったとしたらやっかいです。
このような不確かな状況で先に義務を果たさなければならないとしたら公平に反することになります。
そこで、確実に義務を果たしてもらえる証明がない場合に、自分も拒否できるかが問題となるのです。
例えば、AがBに対し、後払いの特約つきでパソコンを売却した場合に、AはBが多額の借金をして破産寸前だといううわさを聞き不安になり、保証人などを立てるようBに要求し、これに応じてもらえなかったらパソコンの引渡しを拒否できるかという問題です。
民法の改正案の段階では、法制化する可能性が議論されましたが、見送られました。
ですが、解釈上認める見解が有力であり、裁判例でも認めているものがあります。
それぞれのケース次第ですが、当初の想定と異なり財産状況が悪くなっている場合、支払ってもらえることに何らかの保証がないときは、拒絶できる可能性があります。
再度の請求
前記したように、適切に商品や代金などを差し出した場合、相手は義務の実行を拒絶できないことになります。
ですが実際には、「少し待ってほしい」などと言われ、好意で猶予期間を与えたり、事実上待たざるをえなくなったりして、しばらく間が空いてしまうことがあります。
このような場合に、再び請求する際、自分も提供し直さなければいけないのかという問題が起こります。
待たせている相手方に責任があるのだから、抗弁権は消滅するとも考えられます。
しかし、その後、ほかに譲渡して商品が手元にないのに代金を請求できたり、財務状況が悪化して支払見込がないのに商品の納入を強制できたりすることになりかねません。
例えば、AがBにパソコンを売却したが、在庫がなかったため提供された代金をAが受け取らなかった場合、後日、AはBからパソコンを要求されたとき、代金との引換えを請求できなくなるかという問題です。
結論としては、抗弁権を失うものではなく、継続して提供しなければならないとされています。かえって公平に反する結果となりかねないからです。
このことと関係して気をつけるべき問題は、解除との違いです。
債務不履行の場合に、一方的に契約を解消することができますが、そのためには履行の提供をしておく必要があります。
この場合には、再度の提供は不要とされています。
なぜなら、契約を解消してしまうため、本件制度のような公平性や簡易かつ迅速な取引の要請といった、契約関係の存続を前提とした趣旨が妥当しないからです。
まとめ
- 相手が義務を果たそうとしない限り、自分も義務の実行を拒否できる制度です。
- 制度の趣旨は、当事者間の公平性の確保、合理的な意思に資すること、取引の簡易迅速性の要請に応えることにあります。
- 原則として一つの契約から生じた対立する債務の存在が必要です。債権譲渡や債務引受によって当事者に変更があったとしても新当事者に対して主張することができます。
- 弁済期が共に到来している必要があります。
- 契約後の財務状況の悪化を理由に、義務の実行を拒絶できることがあります。
- 一度商品等を提供したとしても、時間をおいて再度請求するときは改めて提供する必要があります。