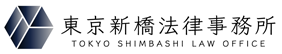〇 わからないことだらけの訴訟手続
当事者の任意交渉や支払督促等の一連の手段を用いても債権回収が実現しない場合には、最終的に訴訟の提起という手段をとることになります。頑なに債務を支払おうとしない債務者に対しても、訴訟を提起し、勝訴判決を得ることができれば債権回収の実現に向けて大きな進展となります。
では、裁判を行うにあたってその手続は具体的にどのような流れになるのでしょうか。「裁判所の法廷はイメージできるけれども、民事裁判が具体的にどのような流れで進行していくかはまったくわからないし、想像もつかない」といった方(特に初めて裁判をおこなう方)がほとんどなのではないでしょうか。
そこで、このページでは、まず最初に一般的な訴訟手続の流れについて概観の説明を行いたいと思います。
また、裁判の手続きの流れを知ると、たくさんの疑問に思う点があると思います。一例ですが、訴えを提起するにあたっては、裁判所に対してどのような手続きを取る必要があるのか、そもそも、どの裁判所に対して訴えを提起すべきなのか、また、訴えを提起できたとしても、その後、法廷で何をする必要があるのか、逆に法廷で何もしないとどうなってしまうのか、そして、裁判の最後には判決が下されますが、判決に対して不服がある場合にはどうすればよいのか…。
といった感じに多くの疑問点が生まれると思います。そこで、このページでは、具体的な事例を1つ挙げて、皆様が抱くであろう具体的な疑問について説明を行いたいと思います。
〇 訴訟手続の流れの概観
まず、訴訟がどの様な流れで進行するのか、概観をみてみましょう。一般的な訴訟手続は下記の表の様な流れで進行します。

初回の口頭弁論のことは「第1回口頭弁論」と呼ばれます(④)。第一回口頭弁論では、訴状および答弁書の陳述や証拠の提出が行われます。そして、たいていの訴訟では1回の口頭弁論では十分な審理が尽くされないので、後日に必要に応じた回数の口頭弁論が開かれることになります(⑤)。そして、十分な審理が尽くされたと裁判所が判断した段階になると、裁判所は口頭弁論の終結を宣言して、審理は終了します。そして、裁判所から判決が言い渡されるのです(⑦)。裁判所の判決内容に不服がある場合には、裁判所に対して判決言渡期日から2週間以内に控訴ができ、控訴がなされた場合には、第二審(控訴審)の手続きが開始することになります。一方で、2週間控訴の無い場合には、判決が確定し訴訟が終了することになるのです(⑧)。まず、訴えを提起したい者(以下、「原告」とします)が訴状を裁判所に提出することにより、裁判は開始します(①)。提出された訴状は、訴状として適切な記載事項が記入されているか形式的に審査がなされ、問題がない場合にはその訴状が裁判所から訴えの相手方(以下、「被告」とします)へ送付されることになります(②)。訴状が送られてきた被告は、訴状に記載されている内容について認否等を答弁書にして裁判所へ提出します(③)。ここまできてようやく口頭弁論―皆さんがよく想像される裁判所での審理―が行われることになるのです。
〇 事例から考える
ここまで、一般的な訴訟手続について確認をしました。そこで次は、具体的な事案を1つ挙げて、皆様が抱くであろう疑問や訴訟手続の具体的な中身について説明を行いたいと思います。
(事案)
自動車部品メーカーX社(代表取締役社長B、顧問弁護士C)は「取引先であるY社に自動車部品を100万円で売却した」と主張して、その支払いをY社に請求しました。しかし、Y社は「その自動車部品を購入した事実は無く、試作品のため無償で譲渡された」と反論して、100万円の支払いに応じません。現在、本件自動車部品はYの工場に置いてあります。しかし、一連の経緯を明確にした書面はX社もY社も持っていません。
X社の法務部に勤務する従業員Aさんは、この問題を解決してY社から100万円を回収するように、との業務命令を受けました。100万円を回収せよとの業務命令を受けた従業員Aさんは、訴訟で100万円を回収する選択をしました。
Aさんは、訴訟によりY社から債権回収をおこなうことを決めたので、まず裁判所へ訴えを提起することになります。では、Aさんは訴えを提起するにあたり、どのような手続きを取る必要があるのでしょうか。
前述のとおり、訴訟は訴えの提起によって開始します。訴えの提起は、訴状を裁判所に提出して行うので、Aさんは裁判所へ訴状を提出することになります。訴状には当事者(Aさん)及び代理人(弁護士等)と請求の趣旨及び原因を記載する必要があります(民事訴訟法133条)。もっとも、簡易裁判所での裁判においては訴えの提起が口頭でなされてもよいという規定もあります(民事訴訟法271条)。また、訴え提起の際には、所定の手数料を支払う必要があります(これを提訴手数料といいます)。
ところで、ここまで訴えの提起の具体的な内容について指摘をしましたが、そもそもAさんは、日本中のどの裁判所に訴えを提起することができるのでしょうか、また、どの裁判所へ訴えを提起するべきなのでしょうか。この問題のことを裁判管轄の問題といいます。
管轄は法律の規定や当事者間の合意の有無、被告の応訴や訴訟の目的物の価額等から判断されます。一例ですが、仮に管轄している裁判所が複数ある場合は、原告がいずれかを選択することができます。また、当事者間の合意で裁判所を決めることも可能です(このような管轄の類型を合意管轄といいます)。また、訴訟の目的物の価額が140万円以下である場合には地方裁判所ではなく簡易裁判所への訴えの提起も可能になります(このような管轄の類型を事物管轄といいます)。
本件の場合、Aさんが債権回収を行おうとしている債権額が100万円であることから、140万円以下ですので、地方裁判所ではなく簡易裁判所への訴え提起も可能となります。ただし、少額訴訟手続へ移行することは出来ません。
万が一、管轄に手違いがあった場合は、事件は適切な管轄の裁判所へ移送されることになります。適切な移送が行われる限り、管轄を間違えてしまうことで、訴えが却下されることはありません(民事訴訟法16条)。
訴えの提起先が決まったところで次に問題となるのが、誰が訴訟追行するのかという問題です。日本の民事訴訟制度は、弁護士強制制度を採用していないため、当事者自らが訴訟追行できます。当事者自らが訴訟を行うことを本人訴訟といいます。
しかし、本件をみてみるとAさんはX社から業務命令を受けて本件訴訟を担当している者です。法人が訴訟の当事者となる場合には、その代表たる者が訴訟を追行する権限を持つと規定されています。つまり、本件訴訟で訴訟を追行する権限を有するのはAさんではなく、X社の代表取締役社長であるBさんということになります。もちろん、Bさんは訴訟追行を代理人に委任することも可能ですが、代理人は原則弁護士でなければならないのです(弁護士代理の原則(民事訴訟法54条))。以上の理由から、Aさんは顧問弁護士Cに訴訟の代理人を依頼すべきであるといえます。
ここまでで、訴訟の提起が完了しました。いよいよ、具体的な審理―口頭弁論に入ることになります。では、X社は、審理の段階では何をする必要があるのでしょうか。また、何もしないとどうなってしまうでしょうか。
一般的に、民事訴訟の審理の原則としては、①審理は一般に公開された法廷で行わなければならない、という公開主義、②審理は口頭で行わなければならない、という口頭主義、③審理に直接参加した裁判官が判決しなければならない、という直接審理主義、④訴訟の審理においては、当事者双方にその主張を述べる機会を具体的に与えなければならない、という双方審尋主義という4つが挙げられます。その様な原則の下、当事者は審理の対象である権利義務関係が存在するか否かを巡り、自らの主張が認められる様に攻防を繰り広げるのです。
そして、民事訴訟法の基本原則の一つとして挙げられるのが、“事実や証拠など判決の資料となるものの収集は当事者が責任と権能をもつ”という考えの弁論主義です。弁論主義には3つの意味があります。
①当事者者双方が提示していない事実を、裁判所は判決の基礎にすることができない(第一テーゼ・第一準則)。
②当事者間に争いのない事実については、裁判所はそのまま認めなければならない(第二テーゼ・第二準則)。
③裁判官の職権による証拠調べは認められない(第三テーゼ・第三準則)。
本事案においても、これらの原則に則って、口頭弁論を進行していくことになります。つまり、法廷でX社Y社も主張していない事実は判決の基礎には用いられず、また、当事者間に争いのない事実については、裁判所はそのまま事実認定を行います。加えて、証拠の提出については、裁判官が職権に基づいて行ってくれるものではないので、当事者であるX社自らが、証拠の収集・提出を行う必要があります。
もっとも、本事案では、XY間の契約の一連の経緯を明確にした書面は、X社もY社も持っていません。XY間の自動車部品の受け渡しが、X社が主張するように売買に基づくものなのか、はたまた、Y社が反論しているように試作品の(無償)贈与なのか、明らかになっていません。そこで、仮に、売買・贈与の存在がともに明らかにならなかった様な場合、裁判所はどのように判断をすることになるのでしょうか。
当事者間で真実の存否に争いがある場合には、事実は証拠によって認定されます(証拠裁判主義)。そして、前述の通り、証拠の収集・提出は当事者の権能と責任の下行われます。しかし、最終的に当事者から提出された証拠では、事実の存否が明らかにならない場合があり、そのような場合には、証明責任に従って判断されることになります。
証明責任とは、「裁判にあたって裁判所又は裁判官がある具体的事実の存否について確信を抱けない(真偽不明の場合=ノンリケット)場合に、当該事実の有無を要件事実とする法律効果の発生ないし不発生が認められることにより被る、当事者一方の不利益」のことをいいます。
本件でX社は自動車部品の売買契約(民法555条)に基づく代金支払請求をしていますので、その要件事実である当事者間で①売買対象物移転の約束が成立していたこと、②代金支払約束が存在していたこと、について証明をする必要があります。ですので、仮にX社側が売買契約の存在を明らかにすることができなかった場合には、X社の請求は認められないむねの判断(請求棄却判決)が裁判所により出されることになるのです。
最後になりますが、訴訟の終了について少しだけ説明をしたいと思います。民事訴訟は必ずしも、判決で終わるとは限りません。判決以外にも、原告による「訴えの取り下げ」や「訴訟上の和解(簡易裁判所ではそれに代わる「決定」の制度)」、相手方による「請求の認諾」または「放棄」などがあるのです。簡易裁判所や地方裁判所では、判決による終局よりもむしろ、それ以外の方法による終局区分の方が割合が多いといわれています。
本件においても、X社としては判決に拠らずとも和解交渉等によって債権回収を図ることが考えられます。