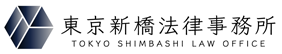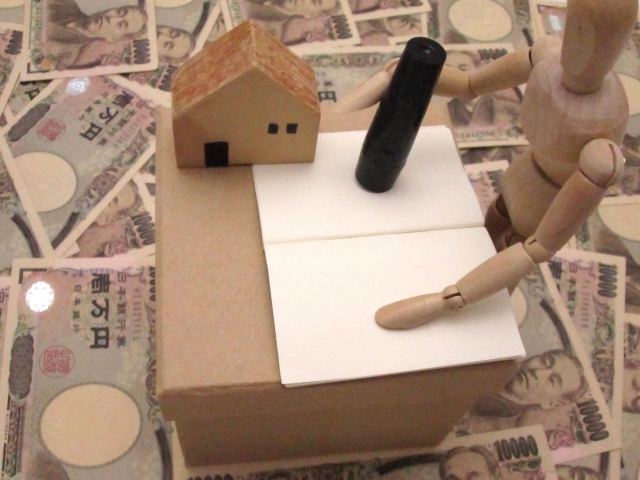
目次
■はじめに
■まとめ
■はじめに
明治以来、根抵当権は各種取引を行う際の重要な不動産担保制度の一種として重宝され、発展してきました。
金融機関が住宅ローンを取り扱うようになり、それに伴う抵当権制度の利用を積極的に行っていますが、このようなケースを除いて考えれば、日本における不動産担保制度の主力は、根抵当権にあるといっても過言ではありません。
このように重要な制度ですが、実務色が強く、なかなか理解がしづらい面があることも否定できません。
細かい部分については必要に応じてその都度調べるとしても、基本的な部分については理解しておく必要があります。
ここでは、根抵当権に関する基本的な性質について解説していきます。
■ポイント1~重要な性質
まず、この制度特有の問題に入る前に、その理解の前提となる担保物権一般の性質について簡単に触れておきます。
・付従性
債権があることではじめて存在できるという性質をいいます。
これは担保権である以上、守るべき債権の存在が必要だからです。
もしはじめから存在しなければ成立しませんし、あとで存在しなくなれば一緒に消滅することになります。
ただし、その権利の種類によってどの程度までこの性質が認められるかは異なります。
・随伴性
債権譲渡などにより、債権が別の人に移ると一緒に移転するという特性です。
これも債権を担保するという目的から導かれます。
これから述べていくように、これらの一般的な性質を維持することで理論的な一貫性を保ちつつ、実用的な権利としていかにうまく運用していくかが重要な視点となります。
■ポイント2~歴史的背景
制度の本質を理解するためには、その歴史的な経緯を知ることも大切なことです。
当初、この制度は明確な規定が置かれていませんでした。
戦後しばらく経ってからようやく専門の規定が置かれるようになりました。
1972年のことです。
それまではどうしていたかといいますと、判例などの実務慣行によってなんとかうまく処理されていました。
ですが、世の中の仕組みが複雑なものになるにつれ、目に見えないルールで処理するには限界が感じられるようになり、これまでの慣行を参考に明文化することにしました。
・よくある2つの取引
従来からの典型的な取引は次の2つに分けられます。
一つは「継続的商品販売契約」です。
例えば、医薬品メーカーであるX社が、小売業者であるA社に対し、自社で製造している甲薬品を継続的に販売している場合に、5,000万円を限度とした掛売りを認めているとします。
つまり、最大で5,000万円(+約定利息と遅延利息)の回収が焦げつくおそれが生じます。
当該取引の場合、個々の債権と債務は、X社が甲薬品を販売するたびに発生し、A社が弁済を行うたびに消滅するということが繰り返されます。
そして通常は、付従性によって担保権も消滅してしまいます。
そこで、個々の取引による影響がない担保権が必要となるのです。
もう一つの典型的な取引は「当座貸越契約」等の銀行取引です。
例えば、Y銀行とAとの間で当座勘定取引契約が存在するとします。
当座勘定取引契約というのは、取引先が銀行に開設した当座預金口座に資金を預け、支払人を当該銀行として振り出した小切手や、当該銀行を支払場所として振り出した約束手形、引き受けた為替手形に対する「支払委託契約」のことです。
AがY銀行を支払人として小切手を振り出した場合、Y銀行としては、Aの預金残高の範囲内で支払いに応じる義務があることになります。
つまり、預金残高が不足しているときは支払ってもらえないわけです。
これでは都合が悪いことがありますので、残高が不足していたとしても一定額の範囲で支払ってもらえる契約を併せて結ぶことがあります。
これを「当座貸越契約」といいます
例えば、500万円を限度とする当座貸越契約がなされた場合に、口座残高が300万円でY銀行を支払人とする500万円の小切手をAが振り出し、Yがその支払いをしたときは、差額200万円についてAに貸し付けたのと同じ扱いとなるわけです。
こちらの契約も、貸付けが生じるたびに債権が生じ、弁済するたびに消滅することが繰り返されます。
そして通常の担保権であれば毎回設定しなければならないことになります。
以上2つの取引例に共通するのは、具体的で継続的な信用取引契約であるということです。
後述するように、現在の制度では、上記の典型的な取引以外の形態もその対象としています。
ですが、もともとこのような取引を対象として利用されてきたということは覚えておいてください。
・必要性
通常の抵当権では、債権の発生のたびに設定し直さなければならないわけですが、これでは煩雑で、とてもビジネスの分野では実用的ではありません。
そこで、債権が消滅してもなくならない抵当権が必要とされたわけです。
・新たな形態
これまで見てきたように従来の取引形態では、具体的な継続的契約(基本契約)が存在していました。
ですが、このような取引関係にある当事者が、これまでとは異なる契約を結びたいと考えることも自然なことです。
例えば、X社がAに対し甲薬品を継続的に販売している場合に、将来的に乙薬品も販売したいことがあります。
従来の方法では「甲薬品」と限定してしまっているため、「乙薬品」には対応できません。
また、Y銀行とAとの間で「当座貸越契約」を結んでいる場合に、将来的に「継続的手形割引契約」を結ぶことも考えられます。
しかし、あくまで別の契約ですから対応することができません。
このような場合に備えて、あらかじめもっと広い範囲で担保できるようにしたいと考えられるようになりました。
具体的には、「X社がAに対し販売する医薬品売買契約から生ずるすべての債権」、「Y銀行とAとの間で行われるすべての銀行取引」という定め方です。
一見なにも問題がないように思えるかもしれませんが、従来とは大きく異なる点があります。
ここで問題なのは、現時点では具体的に存在しない契約から生じるものも対象にしている点です。
これまでの典型的なケースでは、あくまで具体的な契約が存在していたのです。
さらに、ここまで来るともっと単純な発想も現れます。
そもそも限定を加える必要なんてないのではないかというものです。
つまり、「XのAに関するすべての債権」という単純な定め方でもいいのではないかというのです。
このように、従来とは異なる新たな問題点が出てきたことから立法的な解決が必要となりました
結論から言えば、なにも限定のないものは認められませんでしたが、担保権の基本的な性質を損なわない範囲でできるだけ実際の要望に沿うように理論構成されています。
それでは詳しく見ていきたいと思います。
■ポイント3~主な特徴
・基本契約が不要であること
通常の抵当権であれば、なんらかの被担保債権が具体的に存在することが必要となります。
そして、根抵当権においても従来であれば、継続的な契約が具体的に存在していることが一般的でした。
しかし、このような債権的な契約は必ずしも必要ないこととされました。
つまり、前記の例でいえば、未だ締結されていない将来の契約を対象とした、「医薬品売買契約」や、「銀行取引」のようなものも担保の対象として定めることが認められるようになったのです。
個々の債権契約とは関係なく存在できることから、具体的な取引前に設定できますし、取引があった後、その取引について弁済があり、当該債権が消滅したとしても、根抵当権自体は消滅しないことになります。
このように、一見すると付従性が完全に否定されているようにも見えます。
債権者が当該不動産について差し押さえや競売を申し立てるなどすると、根抵当権の対象が特定の債権に定まるのですが、定まった後は付従性が肯定されています。
ですので完全に否定されているわけではなく、担保制度としての理論的一貫性は保たれていることになります。
・対象の限定
どのような債権であっても担保されるわけではありません。
取引に基づいたものなど一定のものに限定されています。
前記した例ではすべて取引に起因したものだけでしたが、それにとどまらず拡大されています。
1.具体的な継続的取引に基づくもの、2.一定の種類に基づくもの、3.取引以外の特定の原因により継続的に発生するもの、4.小切手や手形に基づくものです。
「1.」は、従来からの典型的なケースのことです。
つまり、「X社とAとの間の甲薬品の供給契約」、「Y銀行とAとの間の当座貸越契約」など、特定されたもののことです。
「2.」については、種類で範囲を特定できればいいので、具体的な契約が存在する必要はありません。
例えば、「売買取引」や、「銀行取引」という定め方です。
これにより、X社のAに対する甲薬品の売買代金だけではなく、乙薬品に関するものも担保されます。また、Y銀行については、当座貸越契約だけでなく、手形割引契約に関するものも担保されることとなります。
「3.」については、これまでの考え方と大きく異なります。
これまでのケースでは、すべてなんらかの取引が存在していました。
ですが、取引以外で継続的に発生する債権も存在するため、これも対象にすることを認めたのです。
具体的には、工場からの排液に基づく損害賠償請求権や、酒類の移出に基づく酒税債権が挙げられます。
あくまで特定性や継続性が求められるため、「将来に渡る一切の不法行為に基づく債権」などは対象とできません。
「4.」についてですが、仮にY銀行がAのために手形の割引を行った場合において、それが不渡りとなったとき、YはAに請求できますが、このようなケースは「2.」の「銀行取引」等の定めをすれば担保されます。
そこで、「4.」が独立した意味をもつ場面が問題となります。
割引の依頼人であるAではなく、振出人Bや裏書人Cに請求していく際に意味がでてきます。
つまり、BやCに対して別途根抵当権をもっていた場合に、それによって担保できるということです。
要するにたまたま振出人や裏書人に対して根抵当権をもっていた場合に使われる規定ということです。
いわゆる「回り手形」対策です。
そのため、割引を行う金融機関を想定した規定と考えられます。
ですが、金融機関以外でも「4.」を定めているケースは少なくありません。
一般の企業で回り手形を取得するケースがどれくらいあるのかという問題はありますが、登記をしたとしても税金面で違いはないため、規定しておいたほうが無難かもしれません。
・包括根抵当について
債権の種類について一切制限を設けない、いわゆる包括根抵当については認められていません。
前記した、「XのAに関するすべての債権」のような定め方は有効ではないのです。
付従性を緩和したのであれば、思い切ってこのような定めも有効にしてしまうべきだとする主張もありますが、採用されませんでした。
この制度の本質は、あくまで取引における債権を担保することにあり、付従性の緩和は、債権の成立時期を問わないようにするために行われたからだと説明されています。
・当事者の種類
当事者としては、根抵当権者、設定者、債務者の3者に分けることができます。
設定者というのは、設定契約において自らの不動産を担保として提供する人のことです。
そして、債務者というのは当該根抵当権設定契約において誰の債務を担保するのかという基準となる人のことです。
設定者と同一人物となることもありますが、別人ということもあります。
第三者のために不動産を提供する人のことは特に物上保証人といいます。
■まとめ
・根抵当権は、1972年に明文化される前から慣行として認められていました。
・明文化される前からの典型的な事例として、「継続的な商品供給契約」や、「当座貸越契約」等の銀行取引があります。
・現行法では上記に加えて、一定の種類に基づくものや、特定の原因により継続的に発生するもの、小切手や手形に基づくものが対象となります。
・確定前は付従性や随伴性といった担保権の基本的な性質が否定されています。
・債権の範囲が不明確な包括根抵当は禁止されています。
旧法下の根抵当権は現在でも残っており、専門家でも対応に苦慮するため、気をつける必要があります。