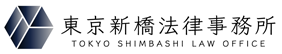目次
■はじめに
■訴状の書式
■被告人の選択
■管轄地
■時効の問題
■まとめ
■ はじめに
昨今、多くの情報がネットを通して検索できるため、
ある程度の規模の債権であれば自分で訴訟を提起して回収しようと考えている方も少なくありません。
この本人訴訟は、弁護士費用がかからない点でコストの低い手段であるため、手続きを正しく守り、主張すべきことを主張できれば十分に債権回収の方法として成立することになります。
もっとも、訴訟を提起するにあたって必要な形式について、普段訴訟と関わりのない人にとってはなかなかわからないことも多く、それが原因となって訴訟が認められなくなることもあるため、この記事で大まかに抑えるべき訴訟提起の注意点を確認いたします。
■ 訴状の書式
民事訴訟法に置いて、訴状について具体的な規定が定められている訳ではありません。
しかし、裁判所は具体的な訴状のフォーマットをHP上に公開しているため、実務はそれをもとに訴状作成されていると考え、自ら訴状を作成する場合にも、そのフォーマットに従って作成することが求められていると思われます。
また、裁判所のHPには、訴状のフォーマットだけでなく、具体的な記載例のサンプルも用意されており、記載に際しての注意点も簡潔に載せられているため、大変参考になります。そのため、自ら訴状を作成する場合は、記載例のサンプルも是非参考にするべきと、思われます。
次に、訴状をタイピングソフトで作成する場合は、フォントのサイズを12ポイントに設定し、A4用紙に片面印刷で作成していくことになります。
そして、印刷枚数が複数枚になる場合は、左端をホッチキスでとめるという処理をする必要があります。
また、訴状のフォーマットにはすでに書くべき事項欄が大まかに設定されているため、それを埋める形で記載していくだけで足りますが、事件名や請求の趣旨、請求原因については、自ら考えて記載する必要があるため、注意が必要です。
この点、事件名は請求内容を示すものとなるため、売買代金を請求する場合は「売買代金請求事件」損害賠償を請求する場合は「損害賠償請求事件」という風に、請求の内容とリンクさせる必要があります。
次に、請求の趣旨は、原告として請求する権利の内容を判決主文の内容で示すものです。そのため、決められた形式に則って記載する必要があります。
形式については、裁判所HPに掲載されている訴状記載例サンプルに従って作成すれば、特に問題ありません。
他方、請求原因については、事件の経緯についての記載が必要となるため、被告の属性や、事件の一部始終についてできるだけ詳細に記載する必要があります。特に、金銭支払いを請求するにあたっては、なぜ自分が被告に対して金銭支払いを要求できるのか、詳細に説明する必要があります。
また、訴状を提出する場合は、訴状と一緒に必要額相当の印紙代を収める必要があります。これは、請求する額が大きくなればなるほど高くなるもので、訴えを提起する側としては無視できない負担となります。
そして、訴状につき何らかの不備がある結果、訴状が却下されてしまった場合、一度支払った印紙代は原則として2分の1しか返還されません。
そうすると、再度訴状を作成しなければならないだけでなく、印紙代についても2分の1は戻ってこないという金銭的な負担もあるため、訴状の書式に従って正しく作成するというのは極めて重要と言えます。
訴状の書式については、本人訴訟がしやすいように裁判所HPにわかりやすい説明とサンプルが掲載されているため、それに従って作成することで、一通りの訴状を完成させることができると思われます。
■ 被告人の選択
訴状を作成するにあたっては、被告についても記載する必要があります。
被告の氏名、住所及び連絡先といった情報が訴状には求められます。
もっとも、被告の住所などについてはなかなか捕捉することが困難な場合も少ないくないため、訴状を作成し、裁判所に提出したとしても、徒労に終わってしまう可能性があります。被告に対して訴状を送達するにあたって気をつけるべき事項を説明します。
まず、通常の被告への送達は特別送達という方法でなされます。これは、郵便を配達する人が記載された被告の住所に訴状を持参し、被告人本人に直接手渡し、あるいは被告との同居人がいる場合は同居人、被告勤務の会社に送達した場合は、会社の管理者に受け取ってもらうことで完了します。
この場合に、被告等が訴状を無事受け取れば問題は発生しませんが、被告等がわざと訴状を受け取らない場合、訴状は裁判所に返送されてしまうことになります。
この場合、被告が訴状記載の住所に住んでいるのに、訴状を受け取らないと判断された場合は、裁判所は訴状を書留郵便で郵送する、付郵便送達という手段が選択されます。
この付郵便送達の場合、裁判所が訴状を郵送した記録が書留記録に残るため、郵送した時点で、送達が完了したという扱いになり、被告が訴状を受け取らなくても、訴状は無事被告に到達したという扱いとなります。
他方、特別送達を行ったものの、そもそも被告が訴状記載の住所に住んでいない場合、付郵便送達は利用できません。この場合は、被告の住民票の移転履歴を検索した上で、再度訴状を修正して、訴状を送達するのが基本となります。
しかし、被告の所在地を検索しても見つけることができなかった場合は、公示送達という方法を選択することができます。
これは、裁判所の掲示板に公示送達の事実を掲示し、2週間の経過をもって送達が完了したとみなす制度のことを言います。
これを利用することで、原告は被告の所在地がわからなくても、被告に訴状を送達したという効果を得られるため、訴状を送れないために、裁判を進行できないという問題を解消することができます。
しかし、公示送達が認められたとしても、被告の所在地が不明なことは変わらないため、訴訟後に強制執行して債権を回収するとなっても、被告の財産がある場所を把握できない可能性もあります。
そのため、公示送達をするかどうかの局面では、その後の債権回収の可能性も考え、訴えを取り下げることもままあります。
被告の選択と、住所の補足という問題は、訴訟を進めるための要件という意味でも重要であり、また、訴訟の後に債権回収を確実に実現するという意味でも重要です。そのため、被告がどこにいるかという問題は常に注意をしながら臨む必要があります。
■ 管轄地
管轄地とは、訴訟を提起すべき裁判所がどこにあり、どの裁判所に提起すれば良いかという問題になります。裁判所は全国各地に存在しますが、どの裁判所に訴えを提起しても良いというものではありません。
原告の被告の所在地が遠くに離れている場合、被告の所在地から到底通えないような遠方の裁判所に訴えを提起するのは不公平な点があるためです。管轄地がどこにあるのかについては、訴訟提起段階で正しく理解しておく必要があります。
まず、原則的な管轄地は被告の所在地から近い裁判所となります。これは訴える者より訴えられる者の方があらゆる準備で後手に回ってしまい負担が大きいため、公平を確保するために被告の所在地から近い場所を管轄地とすることとなっています。
例外として、契約書に裁判の管轄地を特定の場所にする旨の特約を設けていた場合は、その場所が管轄地になります。
この場合は、あらかじめ定めた管轄地で訴状を提出すれば足りるため、債権者としては負担が少ないと言えます。
また、仮に管轄地でない場所に訴状を提出したとしても、被告がそれに応じた場合は、その管轄地は有効となります。本来であれば、原告が管轄違いの訴えを提起した場合、被告は異議申し立てを行って、本来あるべき管轄地へ訴訟を移送することができます。そういった手続きを行わずに応訴した以上、管轄違いで提起された訴訟であっても有効という処理になります。
どの場所で訴訟を進行させることになるのかという問題は、一見些細な問題のようになりますが、訴訟が長期化して、裁判所へ通う回数が増えたりすると交通費の面で大きな負担となります。
また、訴訟に証人を呼ぶ場合などは証人の所在地から遠い場所で裁判することは、証人に負担をかけるため、訴訟の進行に遅延が生じる可能性があります。
円滑に、そして負担を少なく訴訟を進めていくためには、あらかじめどの場所で裁判をするべきなのか、管轄地について契約書で取り決めをしておく必要があると考えられます。
■ 時効の問題
債権回収を行うに際して、時効の問題は無視できない大きな問題です。時効期間が経過してしまい、債務者が時効を援用してしまうと、どんな債権もなかったことになってしまいます。債権者としては、時効期間内に債権回収をするというのが大きな問題となります。
債権者としては、時効期間内に債権回収を実現する手段として、訴訟を提起するという方法があります。この訴訟を提起した場合、進行していた時効は中断され、再び時効期間が1から進行することになります。
そのため、時効期間を経過しそうな場合、訴訟を提起することによって、時効の進行をリセットさせることができます。この場合、具体的な時効の進行がリセットされるのは、訴状を作成し、裁判所に提出した時点になります。
これについて注意すべきなのは、訴状を提出し、被告に訴状が到達した場合、ひとまず訴訟が係属したと言えるので、後から訴えの提起に不備があり、裁判所から訴えが却下されたとしても、時効の中断という効果は否定されません。
しかし、訴状を提出し、被告に到達する前に、訴状記載の内容に不備があったことにより、訴状自体が却下された場合は、時効の中断は最初から生じていなかったことになります。
つまり、時効の経過直前に訴状を提出したにもかかわらず、訴状が却下されたことにより、時効の中断が認められず、時効期間を経過してしまった場合は、債権を消失したのと同様の効果を負うことになります。
時効期間が経過しないよう、余裕を持って債権回収を行う必要があると言えますが、それと同時に訴訟を提起する場合、提出する訴状については、裁判所に却下されないよう、適切な形式を守り、却下されないよう細心の注意を払う必要があると言えます。
■ まとめ
弁護士に頼ることなく、本人の力で訴訟を行う場合、訴状の作成と提出が最初の大きな山場となります。この段階で間違ってしまった場合は、時間と労力、金銭のコストを再び支払う必要があるため、一気に負担の程度が大きくなってしまいます。これを避けるためにも、正しく訴状を作成し、必要とあれば訴状のチェックだけでも弁護士に依頼することで、コストを極力抑えつつ、訴訟を進めていくことができると言えます。