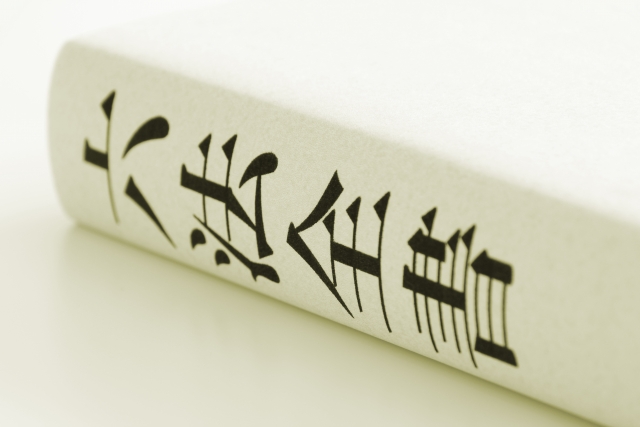
目次
■概要
■登記の種類
■所有権に関する登記
■用益権に関する登記
・地上権
・地役権
・賃借権
■担保権に関する登記
・先取特権
・抵当権
・根抵当権
・質権
■仮登記
■仮処分
■まとめ
■概要
債権回収のために、期限が到来したとして債務者に対し弁済期になった金銭の支払いを催告したとしても、「支払いたくてもお金がない」、「契約は解除した」、「もう時効だ」などといって、任意に支払ってくれるとは限りません。
そんなときには債務者や保証人の財産に強制執行するため、仮差押えをしたうえで債権執行や動産執行をすることが考えられますが、債務者や物上保証人の財産、特に不動産という隠匿しづらく譲渡も難しい、しかも高価な財産があれば債権回収はより容易に、より確実に行うことが可能となります。
ここでは不動産から債権回収を行っていく上で必要となる、抵当権、根抵当権、質権、先取特権といった要(かなめ)となる担保権の登記を中心に、その前提となる所有権の登記を含め様々な登記の種類と権利の特徴を概観し説明していきたいと思います。
■登記の種類
債権回収に関係する権利の登記には、所有権に関する登記、用益権に関する登記、担保権に関する登記、仮登記、仮処分に関する登記など、債権者の権利を実現するために関係する複数の種類があり、それぞれ債権回収にあたって必要となる特徴が異なり、注目すべきポイントも異なるので、ひとつひとつ確認していきましょう。
■所有権に関する登記
抵当権、根抵当権、質権、先取特権といった担保権を設定し登記するには、前提として所有権の登記がなければならないのですが、これは所有権の登記があって初めて抵当権、根抵当権、質権等の担保権や地上権、賃借権等の用益権を設定し登記できるため、すべての権利の登記の前提として、つまり土台として、所有権の登記があることになります。
初めて所有権の登記をする場合に行われるのが、「所有権保存」登記で、2番目以降に行われるのが「所有権移転」登記、または「持分移転」登記で、建物の登記以外で所有権保存登記はあまり見ないと思いますが、これは土地は通常増えたり減ったりしないので、大昔に所有権保存登記をし、いま現在有効な登記は所有権の移転登記が大半のはずだからで、例外として考えられるのは、国有地で権利の登記がされていなかったり、埋立てや海底火山の噴火で土地が新たに増えたような場合くらいです(西之島が代表的といえます。)。
これに対し建物は取り壊したり新たに立て直したりするため、所有権保存登記がよく行われますので、登記記録では普通に登場しますから、甲区1番という権利の登記の最初の部分では、所有権保存登記がなされています。
土地の場合は分筆という、土地を複数に分ける登記手続が行われることがよくあるので、甲区1番に「所有権保存」登記ではなく、「所有権移転」登記が記録されることがよくありますので、必ずしもその不動産の1番目だから所有権保存登記になるわけではないので間違えないようにしましょう。
■用益権に関する登記
用益権(物を利用する権利)は、地上権、地役権、賃借権等いろいろありますが、債権回収にあたって重要なポイントは、担保権設定登記の対象となるかという点にあります。
・地上権の登記
地上権は、ビルや工場を建てる場合などに、「所有権まではいらないよね」というときに、所有権みたいに比較的自由に土地を使える便利で強力な権利で、担保権を設定し、その上で登記することもできます。
・地役権の登記
登記もできますが、直接は抵当権等の担保権の対象とはならず、その代わり承役地に抵当権を設定することで抵当権等の効力が及びます。
・賃借権の登記
賃借権は、賃貸人に対し賃借人が対価として賃料を支払い、代わりに賃貸人に目的物を使用収益することを請求する権利のことです(民法601条)。
抵当権設定登記の対象となりませんが、債権を対象とできる質権の目的とすることができます。
■担保権に関する登記
担保権は法定担保物権と約定担保物権に分かれ、給料債権のような債権者を特に保護しなければいけないような債権や、建物を工事したりするなど他の債権者の債権回収にも有利となる担保価値を高めるようなことをした債権者が不利益を被らないように、法律上当然に発生するものや(意思表示による契約が不要)、利息でもうけたい資本家がお金がなくて困っている人(家を買いたい人や商売をしている人)にお金を貸したときに、将来強制執行したりするのは面倒だし、確実に債権回収したいというときに自分たちの意思で発生させるものがあります。
後者は、お金を貸す時などによく使われ、住宅ローンの場合には抵当権、企業が融資を受けるときなどには根抵当権などが利用されます。
・先取特権
本来債権者が複数いた場合、債務者が債務の全額を完済できないときは、債権額に応じてそれぞれの債権者は債務の弁済を受けることになり、誰かが優先することはなくすべての債権者は対等の立場になり、形式的な平等が図られ、それが正義の観念にも合致します。
ですが、債務者の財産を保護するような褒められるべきことをした債権者の債権や、生活のかかっている労働者の給料債権のようなものは、保護する必要性が高い上に少額であることも多く、債権額に応じて按分されたのではあまりにかわいそうで、実質的な平等を図るべきといえます。
そこで、実質的正義の観点から不平等にならないよう、かわいそうな人が出て、間違っても破産したりしないようにするために「先取特権」という制度ができました。その種類は、「一般先取特権」と呼ばれる生活に密着したもの、「動産先取特権」と呼ばれるお店で買物をしたときなどに関係するもの、「不動産先取特権」と呼ばれる不動産に関するものに大別できますが、登記できるのは、「一般先取特権」と「不動産先取特権」の2つです。
先取特権の登記で重要なのは、普通にお金を貸しただけの抵当権者がいたとしても、不動産の雨漏りを直接直したり、そのためのお金を債務者に代わって支払った人がいたりした場合、その人が優先できるときがあるということです。
・抵当権
抵当権は、後述する質権と同様にお金を返してもらえなかったら、抵当権の実行(つまり、不動産の競売等)により、強制的に債権を回収することができる強力な担保権ですが、質権がお金を借りた人(または借りた人から頼まれて自分の家などを担保に差し出した人)からお金を貸してくれた人に対して、目的物である家などを実際に預けなければいけないのに対し、抵当権の場合は、預けなくていいという違いがあります。
占有移転の必要がないということは、債務者や物上保証人の手元に担保目的物である不動産があるということになり、債務者や物上保証人自身が、不動産の利用収益が可能になるという利点がうまれ、利用勝手のいい担保権として最もポピュラーな担保権となっているわけです。
抵当権の設定対象としては、土地や建物といった不動産所有権のほか、地上権、永小作権、工場財団等にも抵当権が設定できますが、地上権によく似た用益権(物を利用する権利)である賃借権には(賃借権が物権ではなく債権であるため、)設定できない点には注意が必要です。
住宅ローンのような場合には、銀行や信用金庫、農業協同組合等が手配した司法書士がローン契約を結ぶ時点から関与し、手続きを行うことになるので特段問題となることはないと思いますが、金融機関が関与しないような場合は、司法書士と委任契約を結び登記手続を代理してもらうため、自分たちで司法書士を探すことになりますが、司法書士に支払うお金は、国に納める税金の部分は決まっていますが、働いてくれた分に対する対価は、電車賃やタクシー運賃のように決まっていないので、あらかじめ納得いくまで確認しておきましょう。
問題は抵当権が設定され、登記もされた後、お金を返してもらえなくなったときですが、お金を強制的に返してもらうには法律家でも簡単ではないため、素人判断により状況を悪化させる前に、専門の弁護士に相談してください。
・根抵当権
根抵当権は抵当権の一種なのですが、抵当権が特定の債権を担保するための担保権であるのに対し、根抵当権は商売をする人に最適な抵当権です。
例えばロボットを製造するA社が、高性能モーターを製造するB社からモーターを毎月仕入れている場合に、B社としてはA社が代金を支払ってくれないと倒産しかねません。仮に、抵当権を設定しようとするとモーターを売るたびに契約することになり、面倒ですし、国に納める税金やその他の経費が馬鹿になりません。そこで、1回設定してしまえば一定の金額までカバーできる抵当権があればいいわけで、まさにこのようなタイプの抵当権が根抵当権です。
日頃から反復した取引を行う人(法人)が債務者となる担保権ですが、債権を完全に不特定とする包括根抵当と呼ばれる根抵当権は禁止されており、一定範囲の債権を担保すべき債権として契約し、「被担保債権の範囲」として登記しなければならないことになっていることが特徴といえます。
登記特有の問題で債権回収にあたって特に気をつけるべきなのが、「共同根抵当権」であり、普通の抵当権の場合、複数の不動産に同じ抵当権者の抵当権が設定されていたとしても、同じ債権を担保する限り、「債権額」(プラス2年分の約定利息・遅延利息)までしか担保されないのに対し、根抵当権の場合は、普通に登記申請してしまうと、建物から1,000万円、土地から2,000万円というように、別々に根抵当権の最高限度額までお金を受け取ることができてしまいます。
例えば、A不動産とB不動産があり、木村浩一郎さんの永井翔子さんに対する同じ債権を担保するため、債権額2,000万円の抵当権を設定した場合、A、B両不動産を競売してそれぞれ1,750万円、合計3,000万円で売却されたときであっても、木村浩一郎さんの優先弁済を受けられる額は2,000万円までです。
これに対し、根抵当権の場合、木村浩一郎さんは永井翔子さんの持ち家である、A不動産から1,750万円、B不動産から1,750万円、合計3,000万円全額を、売り払った代金から支払ってもらえるため、合計で2,000万円しか優先されないと思っていると債権回収が困難になりかねません。
ただし、根抵当権の登記記録に「共同担保 目録(X)第○号」とあった場合は、抵当権と同様に2,000万円までしか優先されませんので、共同担保目録がついているか注意してください。このような共同根抵当権にするには一定の要件が必要なので、根抵当権設定登記で共同担保関係にしたい場合は司法書士に相談してください。
・質権
質権とは、お金を貸し付けるに当たり、債務者の財物を引き渡してもらい、お金を返してもらうまで返さないという担保権であり、目的物を引き渡してもらう必要のない抵当権や根抵当権と異なり、あまり利用勝手のいい権利とはいえず抵当権ほど利用されてはいませんが、債権者が担保不動産を利用したい場合などでは利用価値があるかもしれません。また、質権は債権質という債権を対象に設定することもできるので、賃借権を目的として質権の設定登記をすることができる点や、抵当権では契約で定めても登記できない違約金を設定できる点が抵当権と異なる利点といえます。
■仮登記
権利に関する登記は、大きく分けると仮登記と本登記があり、普通、登記という場合、本登記のことを指しているのですが、本登記をするには、手続がとても厳格であり、たとえば、登記識別情報(権利証)や、第三者の許可書(農地の売却における農地法の許可書等)が添付できなかったりすると、本登記ができなくなり、登記していない間に不動産を二重譲渡され、権利を取得できなくなったりします。
仮登記をすると本登記をしたときに仮登記の順位で登記したことにしてもらえるため、本登記手続のための要件が整っていないときなどに利用できる登記です。
債務者が担保価値の高い不動産を購入し本登記のための書類が整っていないときなどに考慮されるべき登記といえます。
■仮処分
仮登記に似た登記として仮処分の登記があり、これは土地や建物といった不動産の権利の移転登記を売主がしてくれない場合に、売主が二重譲渡や第三者のための抵当権設定などの担保物権の設定といった、目的不動産の処分行為を防ぎ、自己の権利を保全する手続である仮処分命令を裁判所に出してもらったときになされる登記です。
仮処分の登記は裁判所書記官が登記所に対して嘱託してくれるので、権利者としては裁判所に手続きをとるだけでよく、登記所に対して自ら直接は手続きをとりませんので、仮登記とは異なります。
仮処分の登記が入っている場合、仮処分権利者が将来本登記を得ることになれば、抵触する(矛盾する)登記は抹消されることになるので、債権回収が困難になることが予想されます。
■まとめ
不動産登記の種類は様々ありますが、債権回収にあたって関係してくる登記というのは、その中心として、先取特権、抵当権、根抵当権、質権という担保物権といえますが、その前提となる所有権保存登記、所有権移転登記、そして仮登記や仮処分といった権利を保全する登記も理解しておかなければ確実な債権回収は望めません。
登記に関しては司法書士や登記に詳しい弁護士、担保権の実行については債権回収を専門とする弁護士に相談してください。
