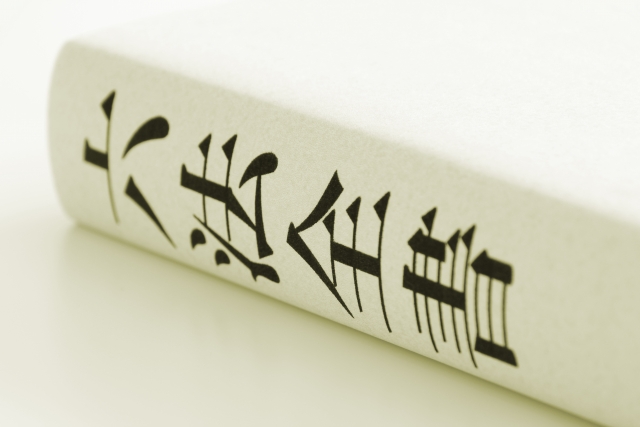
目次
従業員による横領が発覚したら証拠収集が重要です。証拠が不十分な状態で解雇すると不当解雇として逆に訴えられることもあります。
この記事では、従業員が横領した場合の対応や横領の予防策について解説します。
業務上横領とは
横領とは、自分が占有している他人の物を不法に領得する行為のことです(刑法252条1項)。従業員による横領行為の場合には業務上横領罪が問題となります。業務上横領とは、「業務上自己の占有する他人の物を横領すること」です(刑法253条)。通常の横領罪が5年以下の拘禁刑に対して業務上横領のときには10年以下の拘禁刑であり特に重くなります。
横領罪における業務とは、金銭などの財物を委託されて保管する職務のことです。従業員が職務として金銭などを保管する立場であれば「業務上」にあたります。本来の業務に付随する仕事として保管している場合も含まれます。
横領発覚時の対応の流れ
従業員による横領の疑いが生じたときには迅速かつ冷静に行動する必要があります。
被害の把握
従業員による横領の疑いがあるときには事実関係を精査する必要があります。事務処理上の問題で帳簿の記載と食い違っているだけかもしれません。横領の事実があったのか確かめていきます。不確かな状況で従業員に問いただしたり解雇したりしてしまうと証拠を隠されるなどして事態を深刻化させる恐れがあります。
証拠を確保する
横領の疑いのある従業員に問いただす前にできることはやっておきます。本人に横領の嫌疑がかかっていると知られてしまうと証拠や財産を隠されてしまうことがあるからです。また万が一誤解であると逆に責任を追及される恐れもあります。
金銭の横領であれば金銭の入出金の記録を、商品については在庫リストを現物と照らし合わせるなどして調査します。
調査の経緯もできるだけ詳細に記録しておくことが重要です。
|
○年○月○日○時○分:帳簿の記録と集金した金額が一致しないことを経理課長が確認 |
調査記録自体も調査が適切に行われ証拠が適切に集められたことを示す重要な証拠となるからです。
本人からの事情聴取を行う
このようにして調査を行った結果、特定の従業員が横領を働いた可能性が濃厚と判明した場合、従業員に対して横領した金額の損害賠償請求などを検討することになります。
横領が事実だった場合の流れ
従業員が横領していたことが証拠によって裏付けられたときは以下のような対応が考えられます。
|
・損害賠償請求を行う ・解雇など懲戒処分を行う ・業務上横領罪により刑事告訴をする |
損害賠償請求を行う
従業員が横領をしていたのであれば自社に損害が発生していることになります。そのためその損害を従業員に支払うように求めていくことができます。
横領金額がそれほど大きくない場合に給料から天引きするケースがあります。この天引きは法的には「相殺」と呼ばれるものですが、給料の相殺は原則としてすることができません。というのも給料の支払いは労働基準法で厳格に規制されており、その中の「全額払いの原則」に抵触するからです。給料からの控除が認められるのは所得税の源泉徴収や社会保険料の控除、労使協定による組合費の控除などに限られています。
たとえ横領による損害賠償金であっても従業員の同意なく天引きすることは違法となります。従業員の同意があれば理屈上は問題ないことになりますが要件が厳しいため避けた方がいいでしょう。
従業員に身元保証人がいる場合には身元保証人に対する請求も検討できます。ただし、身元保証人については「身元保証ニ関スル法律」により保証期間や責任が制限されています。また2020年4月1日施行の改正民法により改正法施行後に結ぶ身元保証契約に関しては極度額(責任上限額)の定めをしないと保証契約が無効となる点にも注意が必要です(民法465条の2第2項)。
<関連記事>給料の未払いは違法!未払いの給料を会社から回収する方法
懲戒処分を行う
従業員による横領は会社・組織に対する重大な背信行為に当たるため懲戒解雇を検討することになります。あまりに少額のケースであればともかく懲戒解雇ないし普通解雇が一般的な取り扱いといえます。
ただし懲戒解雇をするには就業規則の規定を確認する必要があります。「横領」が懲戒解雇事由として規定されているか確認するのです。従業員に対する懲戒処分について最高裁判所は、就業規則の定めるところにより懲戒処分をなしうるとしています(最判昭和54年10月30日)。
直接「横領」と記載されていなくても、「故意または重大な過失により会社に重大な損害を与えたとき」、「刑法その他刑罰法規の各規程に違反する行為を行い、その犯罪事実が明らかとなったとき」(厚生労働省「モデル就業規則」令和5年7月)などの規定により懲戒解雇できる可能性があります。
ただし、従業員を懲戒解雇する際には当該従業員による横領の事実を証明できなければなりません。仮に従業員による横領の事実を立証できなければ逆に従業員から不当な解雇であるとして未払いの給料などの支払いを求められる恐れがあります。裁判例でも横領の事実の調査が不十分であることを理由に懲戒解雇を無効とするケースがあります。
そのため懲戒解雇をするには十分な証拠を揃えること、横領の疑いのある従業員に弁明の機会を与えること、横領した従業員による返済誓約書を取得することなどが重要となります。
しかし実際に懲戒解雇ないし普通解雇が可能であるのか判然としないケースも多く、また解雇手続きを実施するには就業規則の内容や法令の規定に従う必要があるなど簡単ではありません。そのため解雇をする際には事前に顧問弁護士に相談するようにしてください。
<関連記事>顧問弁護士とは?役割や弁護士との違いを解説
刑事告訴を検討する
刑事告訴とは、犯罪の被害者など一定の告訴権者が捜査機関(警察や検察等)に対して犯罪事実を申告し加害者の処罰を求める意思表示のことです(刑事訴訟法230条~)。犯人の処罰を求める点で単なる被害届とは違います。横領罪は一定範囲の親族を除き親告罪ではないため告訴しなくても処罰可能です。しかし実際には告訴がなければ警察は横領に気づけないため告訴が捜査のきっかけとなります。
刑事告訴のメリット
刑事告訴するメリットとしては、横領した従業員が刑罰を軽減してもらうために積極的に返済する可能性があげられます。被害金額にもよりますが刑事裁判が終結するまでに横領金を返せば執行猶予が付く可能性が高まるからです。他の従業員に対して毅然とした対応をしたという事実を示すことにより再発防止効果も期待できます。
刑事告訴のデメリット
刑事告訴するデメリットとしては、横領の程度が重く実刑になってしまうと収入がなくなり被害金額の回収が難しくなることがあげられます。刑事罰が科されたとしても横領金が返ってくるわけではありません。刑事罰と民事上の債権回収とは別のものだからです。また、横領の事実を証明する必要があるため警察の捜査に協力する必要があり時間や労力がかかります。
横領を防ぐための対策
従業員による横領は業務に精通している者が行っているため発覚までに時間がかかることが多くあります。そのため横領金額が多額にのぼり被害回復が困難なケースもあります。そのため従業員による横領のリスクを低くする予防策が重要となります。
ダブルチェック体制を作る
従業員による横領を防ぐためには現金や預金を扱う業務を透明化することがポイントです。従業員に横領の誘惑を与えないことが大切です。
例えば、出金伝票等を利用した経費の承認制度を取り入れることで自由に出金できないようにすることが考えられます。
預金口座を単独で管理させることもリスクが高いため対策が必要です。通帳管理者と銀行印管理者を分ける、ネットバンキングであればワンタイムパスワード管理者を別人にすることが有効です。
ポイントは一人で多額のお金を扱えないようにすることです。
入出金履歴を定期的にチェックする
従業員による横領を防ぐには不正は必ず発覚するという意識を広めることが効果的です。そのためには入出金の記録を定期的にチェックし、そのことを周知しておくことが有効です。チェックは経営者自身が行うのが確実ですが従業員に任せるのであれば一人の人間に固定せず担当者を定期的に変えた方がいいでしょう。従業員に普段は任せるとしても経営者が不定期にチェックする姿勢を示すことも対策となります。
まとめ
・横領とは、自分が占有している他人の物を不法領得することです。従業員による横領は業務上横領罪として重く処罰される可能性があります。
・従業員による横領が発覚したときは証拠収集や従業員からの聞き取りなどが必要です。
・横領した従業員に対しては、損害賠償請求、懲戒解雇、刑事告訴を検討します。
・横領の予防策のポイントは経理の透明化であり、ダブルチェック体制や入出金履歴の定期チェックが有効です。
従業員の横領でお悩みなら弁護士法人東京新橋法律事務所
従業員の横領対策でお困りの方へ。
従業員の横領が発生した場合には経営への影響を最小限にする必要があり、そのためには迅速かつ適切な調査を実施する必要があります。当該従業員への事情聴取や証拠収集、その後の処分を法的に無難な形で実施する必要があります。
再発防止体制の整備も必要です。経理のダブルチェック体制の導入のほか、横領以外の問題行為への対策も含めた社内研修等も大切です。
経営に隙を与えないコンプライアンス対策を行うには、企業法務に強い弁護士法人と顧問契約を結ぶことが重要です。
当事務所は企業法務に強い弁護士法人です。
解雇や適切な就業規則の作成に限らずビジネスモデル審査、人事労務コンサルティング、広告内容指導などお悩みのことがありましたらお気軽にお問い合わせください。
