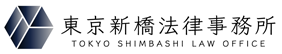建設工事代金は多額になりやすいという特徴があります。そのため未払いとなった場合も影響が大きくなります。
この記事では、建設工事代金の未払い対策や回収方法について解説します。
建設工事代金の未払いが発生する理由
建設工事代金が未払いとなりやすい理由としては以下のようなものがあります。
契約書に問題がある
建設工事代金について前払い金などの約束をしたにもかかわらず契約書に記載しなかった場合には未払いが発生しやすくなります。本来であれば前もって支払われたにもかかわらず工事完了後でなければ請求しにくくなるからです。契約書の作成に際しては細心の注意が必要です。
支払いをする余裕がない
建設工事代金を発注者が支払いたくても支払えない状況もあります。発注者の経済状況が急速に悪くなり工事を完了した時点で支払い能力がないこともあります。
報酬を受け取る前に目的物を引き渡した
建設工事代金の支払いは目的物の引き渡しと同時に行うことが原則です(民法633条)。つまり報酬の支払いがなければ建物の引き渡しを拒否できる可能性があります(商事留置権、商法521条)。
建物工事に関する商事留置権について詳しくは、「工事代金未払いは契約書なしでも回収できる?弁護士に回収依頼するメリットを詳しく解説」をご覧ください。
建設工事代金の未払い対策
建設工事代金の未払い対策としては以下の方法があります。
契約書をきちんと作成する
契約書をきちんと作成していないとトラブルのもととなります。契約書を作成せずに建設工事を行うことは建設業法にも違反します。
建設業法は、建設工事の契約内容を書面に記載して両当事者がその交付を受けるよう定めています(建設業法19条1項)。契約書に記載すべき内容も細かく定められています。
<関連記事>契約書作成におけるチェックポイントと注意事項を解説
正確な見積もりを出す
見積もり金額と実際の工事代金が大きく異なるとトラブルが生じやすくなります。受注前の段階でできるだけ正確な見積もりを出すようにしましょう。
契約締結時に代金の一部を前金として支払ってもらう
契約の中に支払いに関する特約を置いて契約を締結する時点で工事代金のうち一部を支払ってもらうことも重要です。工事途中でも2~3か月おきに出来形部分を支払ってもらうようにするなど工事完成以後に一度に大きな金額を請求しなくて済むような工夫が大事です。
建設業法も、工事完成後に代金を支払う場合だけでなく前金や出来形部分といった支払方法を採用する場合でも、支払方法・時期を契約書に記載するように規定しています(19条1項5号、同12号)。
発注者に連帯保証人を立ててもらう
工事代金は大きな金額であるため信用の高い発注者であっても不測の事態によって支払いができなくなる可能性があります。
そのため、発注者には契約締結時に可能な限り信用の高い連帯保証人を付けてもらうことが効果的です。
災害が起こった場合の責任について定めておく
災害等、不可抗力によって生じた損害をどちらがどの程度負担するかについて予め特約で定めておきましょう。工事途中で災害が起こった場合、この特約を定めていなければ生じた損害を請負人である受注者が全て負担することになりかねません。
建設業法も、天災等に備えた規定を置くよう定めています(建設業法19条1項7号)。
国土交通省の民間工事標準請負契約約款では、天災によって工事途中の建物等に損害が生じた場合には、受注者と発注者とで話合いを持ち、条件が揃った場合には発注者が損害を負担するなどの内容が定めてあります。
また発注者と話し合い事前に工事保険に加入しておくことも重要です。
工事の追加・変更があった場合の対処について定めておく
当初の計画を変更しなければならないこともあります。そのような場合にどのように対処すべきかを予め特約で定めておくことで追加分の工事代金もスムーズに回収できるようになります。
建設業法も、工事に変更が生じた場合の工期の変更や代金の変更について契約で定めておくよう求めています(建設業法19条1項6号)。
また、実際に工事の追加・変更が生じた場合は、その工事に取りかかる前に書面で契約変更を行わなければなりません(建設業法19条2項)。
工事の追加・変更によって工事に要する費用が増加した場合、それを請負人に一方的に負担させることは、「不当に低い請負代金の禁止」を定めた建設業法19条の3に抵触する可能性もあります。
一方的に追加費用の負担を強いられた場合には、発注者にこの条文の存在を指摘して負担額を減らしてもらうよう交渉することが重要です。
遅延損害金の定めを置いておく
支払いが遅れた場合に備えて遅延損害金を定めておくことで早期の支払いを促すことができます。遅延損害金について特段の定めを置いていない場合でも法定利率により請求することができます。しかし遅延損害金の利率を高めに設定しておくことで期限内に工事代金を支払うインセンティブを高めることができます。
紛争が起こった場合の対処法について特約を定めておく
万が一の場合に備えて紛争が起こった場合の解決方法を定めておくことも重要です。建設工事に関する紛争は、まずは訴訟ではなく建設工事紛争審査会によって裁判外での解決を図るのが一般的です。
建設工事紛争審査会とは建築工事の請負契約に関する紛争を解決するために設けられた公的機関です。請負契約の当事者の申請に基づいて、あっせん、調停、そして仲裁といった紛争解決の機会を提供します。
この審査会は、建設工事に関する紛争を解決するためには専門的な事項への理解が必要であることや、受注者が一刻も早く代金支払を受け事業資金を確保しなければならない状態にある等の切迫した場合も多いことなどを理由に、建設工事の請負契約に関する紛争の早期解決を図る専門的な紛争解決機関として設立されました。
請負契約の中にも「この契約について発注者と受注者との間に紛争が生じたときは、建設業法による建設工事紛争審査会のあっせん又は調停によってその解決を図る。」というように定められることが多いです。
建設工事紛争審査会が提供する紛争解決手段は具体的には以下のようなものです。
「あっせん」と「調停」は弁護士や技術委員といった中立な第三者を介した上で、最終的にはあくまで当事者同士の話合いによる解決を目指すものです。
これに対して「仲裁」は、中立な第三者が裁判に代わって判断を下し、当事者は仮にその仲裁判断に納得がいかない場合でも従うことになるという強制力のある解決手段です。また、仲裁判断が下されると同じ論点について訴訟を提起することはできなくなります。
<関連記事>建設業における売掛金とは?回収する方法をご紹介
建設工事の未払い金の回収方法
建設工事代金が未払いとなっている場合には以下のような対処法があります。
立替払い制度の利用をする
元請業者が特定建設業者の場合には、下請業者の建設工事代金未払いによって孫請業者が損害を受けたようなケースでは、元請業者が立替払いをする可能性があります(建設業法41条3項)。
電話や訪問などで催促する
建設工事代金の支払いのめどを確認するには直接発注者に問い合わせることが必要です。返済が遅れる場合には支払期日を明確に約束することが大事です。そうしなければずるずると支払いを引き延ばされてしまうからです。
内容証明郵便の送付
相手と連絡が取れない場合や誠意のある対応をとってもらえない場合には毅然とした態度を示すために内容証明郵便で請求することも選択肢です。必ずしも建設工事代金の請求をする際に内容証明郵便を利用しなければならない理由はありませんが、法的手段の予告などを内容証明郵便で行うことでプレッシャーをかけることができます。
<関連記事>内容証明郵便を出す方法や費用は?弁護士に依頼するメリットも解説
支払督促
支払督促により建設工事代金の支払いを簡易裁判所の書記官から命じてもらう方法もあります。ただし相手から異議が出されると訴訟になるというデメリットがあります。
<関連記事>支払督促とは? 取引先にする場合のメリット・デメリット、手続きの流れを解説
民事訴訟
建設工事代金の未払いがあったときには最終的に民事訴訟により請求していきます。契約書等の証拠を提出し勝訴判決を得ることで相手の財産から強制的に建設工事代金を回収していきます。
強制執行
建設工事代金の支払いが命じられた場合に相手が自分から支払いに応じてくれれば問題ありませんが、支払いに応じないときには強制執行の手続きをする必要があります。預金口座や不動産などの財産を差し押さえて強制的に建設工事代金を回収していきます。
建設工事代金の注意点
建設工事代金の回収が遅れるとそのうち時効にかかって支払ってもらえなくなることがあります。元請業者と下請け業者の力関係により建設工事代金の支払いを求めることが難しいこともありますが、時間の経過により取り返しのつかない状況になることもあります。時効期間はリセットすることもできるため適切に対処することが必要です。
弁護士に相談することで建設工事代金が時効にかかることを防ぐこともできます。建設工事代金の未払いが長期間に及んでいるときには早めに弁護士に相談することが重要です。
<関連記事>売掛金の時効はいつ?未回収にさせないためにするべきこと
まとめ
・建設工事代金の未払いを防ぐには適切な契約書を作成することがポイントです。
・正確な見積もりをすることや代金の前払い、連帯保証人をつけてもらうことも有効です。
・建設工事代金は長期間放置すると時効にかかります。弁護士に早めに相談して時効対策をすることが大事です。
建設工事代金の回収でお悩みなら弁護士法人東京新橋法律事務所
当事務所は事業で生じた債権の回収に強い事務所であり実績も多数あります。
当事務所では、未収金が入金されてはじめて報酬が発生する成功報酬制です。
「着手金0円(法的手続きを除く。)」、「請求実費0円」、「相談料0円」となっておりご相談いただきやすい体制を整えております。
※個人間や単独の債権については相談料・着手金がかかります。くわしくは弁護士費用のページをご覧ください。
債務者が行方不明など他事務所では難しい債権の回収も可能です。
「多額の未収債権の滞納があって処理に困っている」
「毎月一定額以上の未収金が継続的に発生している」
このような問題を抱えているのであればお気軽にご相談ください。
※債務の返済ができずお困りの方はこちらの記事をご参照ください。