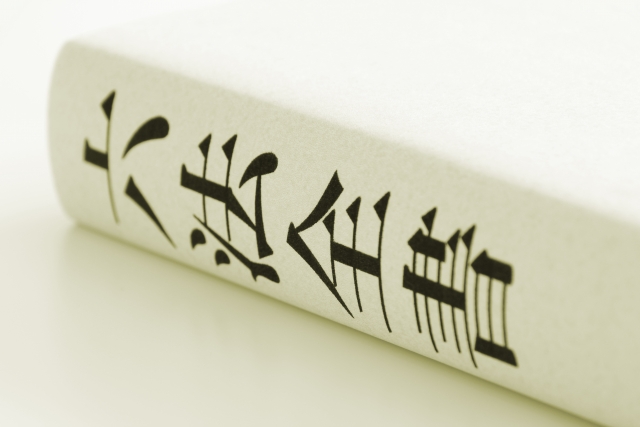
目次
債権には時効がありますが各債権の種類や発生時期によって時効期間は異なります。時効にかからないためには時効期間を把握して早めに対策をとることが重要です。
この記事では各債権の時効期間や時効にかからないための対策について解説します。
債権の時効とは
多くの権利には時効が存在します。時効というのはある事実状態が一定期間継続した場合に、その事実状態を維持するための制度です。権利がしばらく使われなかった場合には権利がないものとして取り扱うことになります(消滅時効)。お金を人に請求できる権利を金銭債権といいますが金銭債権を使わずに放置していると消滅するということです。ただし、債権によって時効期間が異なることがあります。
各債権の消滅時効期間まとめ
2020年4月1日以降に発生した各債権の時効期間の原則は以下の通りです。
|
時効の起算点 |
時効期間 |
|
権利を行使することができることを知った時 |
5年間 |
|
権利を行使することができる時 |
10年間 |
※時効期間を数え始めるときは原則として翌日からです(民法140条本文)。
これはあくまで原則としての期間であり各債権によって時効期間が異なることがあるので注意が必要です。具体的に各債権の消滅時効期間を見ていきます。
売掛金債権|原則5年
商品やサービスを後払いで提供した場合には売掛金債権が発生します。売掛金については5年または10年で時効にかかる可能性があります。売掛金について支払期限が特にないときにはいつでも請求できることから契約日の翌日から数えて5年で時効にかかる可能性があります。支払期限があるときにはその日の翌日から5年で時効にかかる可能性があります。
請負代金債権|原則5年
請負代金債権の場合には、支払期日があるときにはその翌日から5年で時効にかかる可能性があります。支払期日がないときには引渡した翌日から5年で時効にかかる恐れがあります(引渡しが要らないものについては仕事完成の翌日から5年)。
家賃・地代などの賃料債権|原則5年
家賃や地代などの賃料債権については一定期間ごとに支払期日が設定されていることから、各期日の翌日から数え始めて5年で時効にかかる恐れがあります。賃料の回収を放置していると次々と債権が時効にかかってしまうので早めに回収に着手することが重要です。
給与・残業代・退職金債権|原則5年(3年)
給与については民法とは別に労働基準法という法律で時効が定められています。労働基準法115条で賃金債権については行使できる時から5年間行わないと時効消滅すると書いてあります。ただし、当分の間は3年(退職手当を除く。)となっています(143条3項)。
貸付金債権|原則5年
お金を貸した場合には貸した人は支払期日に権利を行使できるのでその翌日から5年で時効によって債権を失う可能性があります。期限を付けずにお金を貸した場合には少し厄介です。お金を貸しつける契約のことを「金銭消費貸借」といいますが、消費貸借で返済期限を設けない場合、貸した人は相当な期間を定めて返済を求めることになっているからです(民法591条1項)。そこで貸してから相当期間経過した時から数え始めるとする考え方があります。一方で古い時代の判例に従うと契約の翌日から数えることになっています。債権者としては判例に従って早めに回収するべきです。
不法行為による損害賠償請求|3年~20年
犯罪や交通事故の被害にあったときには不法行為による損害賠償債権を取得します。この場合の時効期間は、原則として「損害および加害者を知った時から3年(人の生命や身体侵害の場合は5年)」、または「不法行為の時から20年」とされます。
<関連記事>債務不履行に基づく損害賠償の時効や条件について解説
※改正法が施行された2020年4月1日より前に生じた債権や債権の種類によっては時効期間が異なることがあります。
時効完成前にできる対応策
各債権は当初の時効期間が経過したとしても時効消滅するとは限りません。一定の行為があると時効期間が更新されたり一時的に完成が猶予されたりします。
内容証明郵便の送付
時効期間が差し迫っているときには一時的に時効の完成を猶予する手続きを検討します。取引相手に弁済を催告することも完成猶予事由とされており6か月間だけですが時効の完成が猶予されます。証拠に残らなければ相手に否定されるリスクがあるため内容証明郵便等を利用します。ただし、催告による完成猶予中に再び催告をしたとしても完成猶予の効果は生じません。
<関連記事>内容証明郵便を出す方法や費用は?弁護士に依頼するメリットも解説
債務承認を得る
相手が債権の存在を承認することで時効期間が更新(リセット)されます。一部入金や分割払いの申し出なども債権の承認の一種です。注意点としては承認したという証拠を残すことが重要です。例えば一部入金では別の理由で支払ったなどと言い訳される恐れがあります。そのため債務承認弁済契約書など明確な形で承認を得ることが望ましいといえます。
<関連記事>債務承認弁済契約書とは?ひな形や印紙について詳しく解説
裁判・支払督促で時効を中断
訴訟などの法的手続きを行うことでも各債権の時効完成を猶予したり更新したりすることができます。債権が確定判決やそれと同一の効力をもつものにより確定したときには時効期間が更新されます。その場合時効期間は10年に伸びます(民法169条)。
ただし、支払督促についてはリセット後の期間が10年に伸びるかという争点があり裁判例が分かれています。仮執行宣言付支払督促については確定しても既判力がないことから10年には伸びないとする裁判例があるため(宮崎簡易裁判所判決令和4年12月13日)、債権者としては元の期間を前提に早めに行動した方が無難です。
時効の更新について詳しくは「時効の中断とは?民法改正による変更点など詳しく解説」をご覧ください。
時効援用とは
時効の利益を主張することを時効の援用といいます。時効は援用することによって確定的に効果が生じます。債務を負っている相手方が時効期間の経過後に「時効が成立しているので支払わない」と意思表示することが時効の援用です。
<関連記事>時効は何年?種類別の期間や注意事項について分かりやすく解説
債権管理で時効を防ぐチェックポイント
各債権が時効にかかるのを防ぐには債権管理が重要です。
債権台帳の定期チェック
会計ソフトやスプレッドシートなどにより債権管理を行いますが、売掛金残高や入金遅れがないかを定期的にチェックすることが必要です。売掛金回収予定表や売掛金残高一覧表、売掛金年齢表など必要に応じて作成することで回収漏れを防ぎます。
請求業務のフロー見直し
債権回収業務がうまくいっておらず時効にかかる恐れがあるときには請求業務を改善する必要があります。例えば、入金遅れの期間に応じてメールや電話による督促、督促状の発送、顧問弁護士への相談などをマニュアル化しておくことや定期的に別の担当者によるチェックを入れるなどシステム化することで債権回収を効率化します。
クラウド債権管理システムの導入
各債権が時効にかからないためには債権管理が重要ですが、専用のクラウド債権管理システムを導入することも有効です。債権回収が一定期間遅れているときにメール等で通知するシステムはスプレッドシートなどにより構築することも可能ですが、専用のシステムを導入することで維持管理の手間を省くことができます。
<関連記事>売掛金管理とは?管理の仕方やトラブルの対処法を解説
まとめ
・債権には時効があり一定期間債権を放置していると時効によって権利を失うことがあります。
・各債権の時効期間の原則は、権利を行使することができることを知った時から5年、または権利を行使することができる時から10年です。ただし、各債権の発生時期や種類によって時効期間は異なることがあります。
・当初の時効期間が過ぎたとしても債権が消滅するとは限りません。時効期間は更新したり完成猶予がされたりすることがあります。
・各債権が時効にかからないためには適切な債権管理が重要です。
債権の時効でお悩みなら弁護士法人東京新橋法律事務所
当事務所は債権の回収に強い事務所です。
回収管理システムを活用し、大量案件も効率的・迅速に対応可能です。
|
・コンビ二振込票発行管理 請求書・督促状にコンビニ振込票を同封します。 ・クラウドシステムからの一括督促(債務者の携帯番号やEメールアドレスの活用) ・自動入金処理 銀行やコンビニ振込による入金情報はCSVファイルを利用してシステムに同期させています。 |
少額債権(数千円単位)や債務者が行方不明など他事務所では難しい債権の回収もご相談ください。
当事務所では、未収金が入金されてはじめて報酬が発生する成功報酬制です。
「着手金0円(法的手続きを除く。)」、「請求実費0円」、「相談料0円」となっておりご相談いただきやすい体制を整えております。
※個人間や単独の債権については相談料・着手金がかかります。くわしくは弁護士費用のページをご覧ください。
「多額の未収債権があって処理に困っている」
「毎月一定額以上の未収金が継続的に発生している」
このような問題を抱えているのであればお気軽にご相談ください。
依頼者様のブランドイメージを守りながら債権回収を行います。
当弁護士法人は債務整理、離婚、相続、刑事事件、企業法務など幅広く対応しており多角的な視点から問題解決に取り組んでいます。お困りのことがあればお気軽にご相談ください。
債権回収以外の主な取り扱い案件については、こちらのページをご覧ください。
※記事の内容は執筆された当時の法令等に基づいております。細心の注意を払っておりますが内容について保証するものではありません。お困りのことがあれば弁護士に直接ご相談ください。
