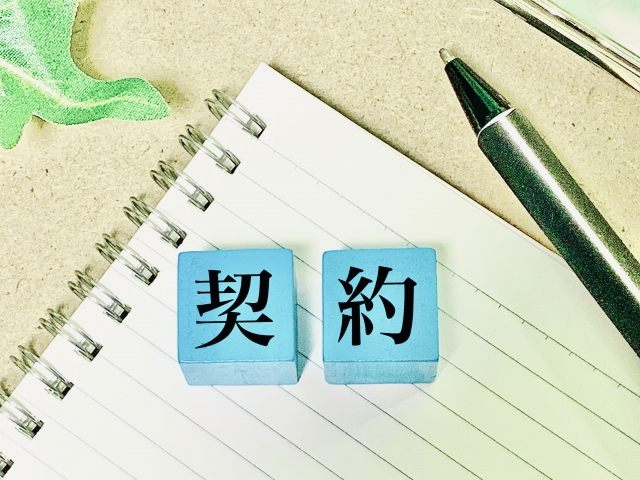
目次
お金の貸し借りなどの際に契約書を作成していなかった場合や、不法行為による損害賠償金が発生しているときには、支払義務や支払方法を明確にすることが大切です。契約書があっても返済が滞っているケースなど債務や支払期日などが不明確なこともあります。このような場合には「債務承認弁済契約書」の作成を検討します。
この記事では、債務承認弁済契約書についてひな形などを含めて解説します。
債務承認弁済契約書とは
債務承認弁済契約とは、契約や不法行為などによって生じた債務について、今現在どのような債務を負っているのかを明確にし、今後どのように弁済していくのかを定める契約のことであり、その内容を書面にしたものを債務承認弁済契約書といいます。
支払いが滞っている売掛金や貸付金、不法行為などの損害賠償金について残額がいくらあるのか、また履行方法を確定させる際に利用されます。ほかにも契約書や借用書を作成していなかった場合に債務と履行方法を証拠に残すために作成することがあります。
また当初の弁済方法を変更するときにも債務承認弁済契約書は活用されます。
金銭消費貸借契約書との違い
金銭の貸し借りをする際に作成される契約書を「金銭消費貸借契約書」といいます。債務承認弁済契約書は金銭の貸し借りだけでなく売買代金や損害賠償金など債務全般が対象となります。
金銭の貸し借りの場合でも貸付けの時点で契約書を作成していなかったり、条件が不明確であったりした場合にも債務承認弁済契約書を作ることがあります。金銭消費貸借契約書があるときであっても支払いが遅れているときには債務の明確化や時効対策のために債務承認弁済契約書を作成する意味があります。
<関連記事>お金を貸した後でも借用書は作成できる?貸し借り後の書類作成を分かりやすく解説
準消費貸借契約書との違い
消費貸借というのは金銭などの代替の利くものを貸し借りすることです。準消費貸借というのは金銭などの代替の利くものを給付する義務がある場合に、その物を消費貸借の目的にすることです。例えば、売買代金の支払い義務が相手にある場合に新たに利息をつけてお金を貸したことにする場合です。
一方で債務承認弁済契約は既存の債務を確認して履行方法を定める契約です。
債務承認弁済契約書を作成するメリット
債務承認弁済契約書には以下のようなメリットがあります。
契約後でも作成できる
債務承認弁済契約書はお金を貸した後など契約後であっても作成できます。売買など通常の契約は書面を作成しなくても成立します(保証契約など例外はあります。)。お金の貸し借りなどの際に契約書を作成しなかったとしても債務承認弁済契約書を作成することで証拠に残すことができます。
<関連記事>口約束のお金の貸し借り|お金が返って来ないときの対処法
公正証書だと強制執行しやすくなる
債務承認弁済契約書は公正証書によって作成することもできます。債務承認弁済契約書を公正証書によって作成し、支払いを怠った場合には直ちに強制執行に服する旨が記載されていると相手の財産を差し押さえることが可能となります。通常は訴訟を起こして支払いを命じる判決をもらわないと相手の財産を差し押さえることはできませんが、あらかじめ公正証書により契約書を作成しておくことで訴訟の手間が省けることになります。ただし、効果が強力であり債務者としてはいつ強制執行を受けるかわからないため公正証書の作成に協力してくれるとは限りません。
<関連記事>借用書は公正証書で作成するべき?確実に債権回収ための手順を解説
連帯保証人の設定が可能
元の契約について書面がないと連帯保証契約を結ぶことが難しくなります。どのような債務について保証するのかわからないからです。保証契約自体も書面でしなければ効力が生じないことになっています(民法446条2項)。元の契約について書面がなかったとしても債務承認弁済契約書を作成することで連帯保証契約がしやすくなります。
<関連記事>保証契約とは?連帯保証契約との違いや民法改正のポイントを分かりやすく解説
消滅時効のリスクを減らせる
お金などを請求する権利には時効があります。一定の期間が経過すると時効により権利を失うことがあります。ただし時効は一定の出来事があると期間がはじめから数え直すことになっています(時効期間の更新)。債務者が債務を承認することも更新事由の一つです。そのため時効期間が迫っているときには債務承認弁済契約書を作成することで時効対策となります。
<関連記事>消滅時効援用における「債務の承認」とは?分かりやすく解説
債務承認弁済契約書のひな形
債務承認弁済契約書には以下のような内容を記載します
|
・債務の発生原因(誤認しないように債務の性質、日付等で特定します。) ・債務を承認した事実と日付(〇年〇月〇日現在) ・承認日現在の債務残高 ・返済方法(一括・分割、返済金額、返済期日、支払方法等) ・遅延損害金 ・期限の利益喪失 ・債権者の署名押印 ・債務者の署名押印 |
債務承認弁済契約書のテンプレートは以下のようなものです。
<記載例>
|
債務承認弁済契約書
債権者〇〇〇〇(以下、「甲」という。)及び債務者〇〇〇〇(以下、「乙」という。)は、以下の通り債務承認弁済契約を締結した。 第1条(債務の確認) 甲及び乙は、〇年〇月〇日現在、乙が甲に対して、(〇年〇月〇日付)〇〇契約に基づく債務として、金〇万円の支払債務を負っていることを確認する。 第2条(弁済期日及び弁済方法) 乙は、甲に対し、第1条の金員を次の通り分割し、甲の指定する下記金融機関の口座に振り込む方法で支払う。振込手数料は乙の負担とする。 1 〇年〇月から〇年〇月まで毎月末日限り、金〇万円
記
振込先:〇〇銀行〇〇支店(普通預金)口座番号〇〇〇〇〇〇 第3条(期限の利益喪失) 乙は、以下のいずれかの事由が生じたときは、甲から何らの催告を受けることなく、甲に対する一切の債務について期限の利益を喪失し、直ちに債務を弁済しなければならない。 1 乙が第2条の分割金の支払いを2回以上怠ったとき 2 乙が、差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき 3 乙が、破産手続開始又は民事再生手続開始の申立てを受けたとき 4 その他乙の信用状態が悪化したとき 第4条(遅延損害金) 乙は、期限の利益を喪失したときは、期限の利益を喪失した日の翌日から支払済みまで、年〇パーセントの割合による遅延損害金を支払う。 この契約を証するため本契約書2通を作成し、各自その内容を確認し署名押印の上、各1通を所持する。
〇年〇月〇日 甲(債権者):住所 氏名 〇〇〇〇 印 乙(債務者):住所 氏名 〇〇〇〇 印 |
※事案によって適切な記載は異なります。実際に債務承認弁済契約書を作成するときは弁護士にご相談ください。
契約書一般の注意事項については、「契約書作成におけるチェックポイントと注意事項を解説」をご参照ください。
債務承認弁済契約書に印紙は必要か
債務承認弁済契約書についても収入印紙が必要となることがあります。
対象の債務を生じさせた契約が印紙税法別表の課税物件名に記載されている契約に当たれば課税される可能性があります(印紙税額一覧表)。
原契約書が未作成または印紙税を納付していない場合
原契約が金銭消費貸借契約や不動産売買契約など課税物件に当たる場合には、印紙税が未納付のため本来の契約書に貼付すべき収入印紙が必要となります。
原契約書が作成済みで印紙税も納付済みの場合
原契約書のうち重要な事項に変更がある場合には課税対象となります(国税庁「No.7127契約内容を変更する文書」)。重要な事項については「印紙税の手引き(国税庁)」において「支払方法や支払期日」などが例示されています。
印紙税額は契約金額によって変わりますが、通常の債務承認弁済契約書はすでに成立している消費貸借契約等の債務額を確認するものにすぎず、契約金額を変更したり新たに成立させたりするものではありません。そのため「契約金額の記載のない契約書」として、200円の収入印紙が必要となります。
ただし、原契約書に契約金額の定めがない場合には債務承認弁済契約書により契約金額が証明されるため「契約金額の記載のある契約書」として課税されます。
動産の売掛金債務や不法行為に基づく損害賠償債務の場合
不法行為に基づく損害賠償債務や動産売買の売掛金債務など課税物件にあたらないものは収入印紙が不要です。
※印紙税は令和6年11月18日時点のものであり内容について保証するものではありません。実際の取り扱いはケースによって異なるため国税庁ホームページをご確認ください。
まとめ
・債務承認弁済契約書とは、既発生の債務の内容や金額を確認するとともに弁済方法を定める契約書のことです。契約書がない場合や支払方法が不明確な場合などに作成されます。
・債務承認弁済契約書を公正証書で作成することで強制執行がしやすくなります。そのため滞納しないように気を付けてもらいやすくなります。
・債務承認弁済契約書には収入印紙が必要となることがあります。
債権回収でお悩みなら弁護士法人東京新橋法律事務所
当事務所は債権の回収に強い事務所です。
回収管理システムを活用し、大量受任も効率的・迅速に対応可能です。
依頼者様のブランドイメージを守りながら債権回収を行います。
当事務所では、未収金が入金されてはじめて報酬が発生する成功報酬制です。
「着手金0円(法的手続きを除く。)」、「請求実費0円」、「相談料0円」となっておりご相談いただきやすい体制を整えております。
※個人間や単独の債権については相談料・着手金がかかります。くわしくは弁護士費用のページをご覧ください。
※借金などの債務の返済ができずお困りの方はこちらの記事をご参照ください。




