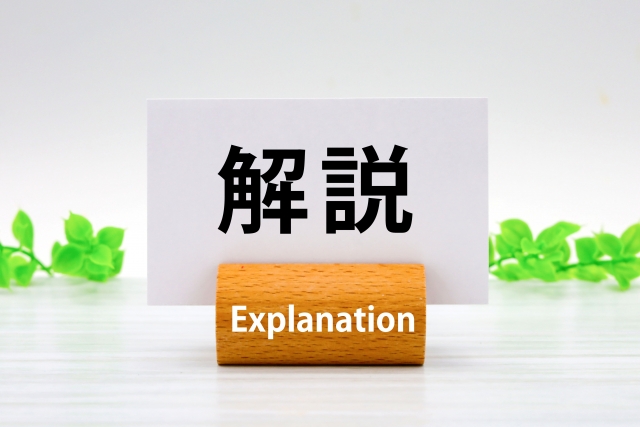
目次
地役権は他人の土地を利用させてもらう権利の一種です。似たような権利として賃借権や地上権もありますがそれぞれ特徴が異なります。地役権は土地の権利を調整することで土地を有効活用することができる権利といえます。地役権と同様の機能は区分地上権で実現できることもありますが登記との関連で全く同じではありません。
この記事では、地役権とは何かについて賃借権や地上権との違いを含めて解説します。
地役権とは
地役権とは、自分の土地の利便性を向上させる目的で他人の土地を使用する物権のことです(民法280条)。他人の土地を一定の目的のために使用収益する用益物権の一種です。
地役権における利便性を向上させる土地を「要役地」といい、他人の土地を「承役地」といいます。つまり、地役権は要役地の利用価値を高めるために承役地に設定される権利であり要役地と承役地という2筆の土地の関係ということになります。
代表的な地役権としては通行地役権があります。これは自分の土地の出入りのために他人の土地を通行させてもらう権利です。通行権のおかげで自分の土地の利便性が高まることになります。他にも発電施設から電力を送り出すために設定する電線路敷設地役権、自分の土地で水を利用するための用水地役権、日当たりを確保するための日照地役権などがあります。要役地と承役地は隣接している必要はありません。あくまで土地の便益を高めるために他人の土地を利用できる関係にあれば良いからです。
賃借権・地上権との違い
地役権と同じような目的で利用される権利として賃借権と地上権があります。これらの権利と地役権との違いについて見ていきます。
賃借権と地役権の違い
土地の賃借権も他人の土地を利用することのできる権利です。しかし賃借権は債権の一種ですが地上権は物権にあたります。債権というのは人に対して一定の行為を要求する権利のことです。一方で物権は物を直接支配して利益を得る権利であり他人の行為が不要です。そのため土地賃借権は賃貸人に対して土地の利用を要求できる権利にすぎないため権利としては基本的に強くありません。土地所有者が変更になったときには権利を認めてもらえないおそれがあります(特約により登記した場合には保護されます。)。また賃借権を設定した場合には土地を直接利用する権利が賃借権者に移ってしまうため地主が利用しづらくなるという問題があります。
これに対して地役権の場合には物権であることから登記を備えることで所有者の変更があった場合など第三者に対しても対抗することができます。また設定目的の範囲で土地を利用する権利にすぎないため土地権利者の利用と併存することが可能であり土地を有効活用することができます。
<関連記事>物権とは?債権との違いを分かりやすく解説
地上権と地役権の違い
地上権も他人の土地を利用することのできる権利です。地上権とは、工作物や竹木を所有する目的で他人の所有する土地を使用する物権のことです(民法265条)。地役権と同じ物権ですが自分の土地の便益のためという目的は不要です。地上権の場合も賃借権と同様に土地の使用収益権が地上権者に移るため土地権利者も土地を引き続き利用したい場合には問題があります。ただし、地上権には空間や地下に階層的な範囲を指定して設定する「区分地上権」という種類があります。そのため送電線を敷設する際など地役権ではなく区分地上権の方法も考えられます(山岳地帯のように上下の範囲を指定することが難しいケースは考えられます。)。地上権は一筆の土地の一部に登記することはできませんが、地役権は承役地の一部に設定して登記することが可能であるという違いもあるためケースによって使い分けることになります。
地役権と抵当権
地役権は要役地から分離して譲渡することや他の権利の目的とすることはできません(民法281条2項)。また抵当権の設定対象となるのは、民法上は不動産、地上権、永小作権とされています(369条)。そのため地役権そのものに抵当権を設定することはできません。地役権は要役地の所有権などに従属する性質があるため、原則として土地所有権の譲渡により同時に移転します(281条1項本文前段)。また要役地に設定した別の権利の目的となるため(後段)、地役権設定後に要役地に抵当権が設定されれば抵当権の効力は地役権にも及ぶため抵当権が実行されたときは買受人が原則として地役権者となります(地役権の設定の際に別段の定めをすることで権利を移転させないことはできます(ただし書)。)。
承役地に抵当権が設定される場合
地役権設定登記後の承役地に抵当権を設定した場合には地役権の負担のついた土地を担保にしたことになります。つまりローンなどの返済ができずに抵当権が実行された場合には買受人は地役権の負担付きの土地を取得したことになります。
承役地に抵当権が設定される場合に注意しなければならない点として、登記のない地役権の存在があります。登記がなければ地役権を第三者に対抗することができませんが(民法177条)、登記の不備を主張することが信義に反するような者はここでいう第三者に当たらないとされています。つまり登記がなくても地役権を主張することができます。
最高裁判所は通行地役権の事案において、承役地が抵当権の実行により競売された場合において、最先順位の抵当権の設定時に、すでに通行地役権が設定されており要役地の権利者によって継続的に通路として使用されていることが位置や形状、構造などの物理的状況から客観的に明らかであり、かつ、抵当権者がそのことを認識していたか認識できたときは、特段の事情がない限りは登記がなくても競売による買受人に対して通行地役権を主張することができるとしています(最判平成25年2月26日)。
抵当権による競売だけでなく通常の譲渡においても同様の要件を満たすときは登記がなくても地役権を主張できるため(最判平成10年2月13日)、土地に抵当権を設定したり譲り受けたりする際には事前の調査が重要となります。
※地役権を第三者に主張するには原則として登記が必要です(民法177条)。本記事の事例は特に記述がない限り登記があることを前提としています。
<関連記事>抵当権設定登記とは?費用や手続きの流れを詳しく解説
地役権の設定・登記方法
地役権の設定は以下のような手順で行われます。
地役権の設定
要役地の権利者と承役地の権利者との間で地役権設定契約を締結します。所有権者に限らず地上権者や賃借権者を当事者とすることもできます。また地役権は地上権などと異なり土地を全面的に使用する権利ではないことから矛盾しない限り承役地に対して複数の地役権を設定することもできます。
登記の管轄
登記は管轄の法務局に申請書を提出して手続きを行います。地役権の場合には承役地を管轄する法務局で手続きをします。承役地で地役権設定登記がなされると登記官が職権により要役地でも登記をしてくれます。
登記申請手続き
登記申請書には地役権設定の目的を記載する必要があります。例えば、「通行」、「電線路敷設」、「用水使用」、「日照確保のため高さ◯メートル以上の工作物を設置しない」などとします。地役権は範囲を指定できるため位置や範囲を記載します。例えば、「範囲 北側◯メートル」、「範囲 全部」などとします。特約として民法281条1項ただし書の定め(要役地とともに移転しない)があるときには申請書に記載します。設定契約で地代を定めていたとしても登記事項ではありません。
必要書面
登記申請には以下の書類が必要となります。
|
・登記原因証明情報 ・登記義務者の登記識別情報(登記済証) ・土地所有権に設定する場合には承役地所有者の印鑑証明書 ・地役権図面(承役地の一部に設定する場合) ・代理権限証明情報(司法書士への委任状) |
※ケースによって必要となる書類は異なることがあります。
登記費用
登記申請手続きには登録免許税が必要です。地役権設定登記については承役地1個につき1,500円です(登録免許税法別表第一1.(4))。この他に司法書士費用が数万円程度必要となります。
まとめ
・地役権とは、自分の土地の利便性を向上させる目的で他人の土地を使用する用益物権の一種です。利便性を高める土地は「要役地」、負担を受ける土地は「承役地」といいます。
・地役権の種類としては、通行地役権、電線路敷設地役権、用水地役権、日照地役権などがあります。必ずしも要役地と承役地は隣接していることを要しません。
・賃借権と地役権の違いは賃借権が債権であるのに対して地役権は物権であることなどがあります。
・地役権は要役地から分離して処分ができず抵当権を直接設定することもできません。
・地役権の設定登記申請は承役地を管轄する法務局で行います。
不動産法務でお悩みなら弁護士法人東京新橋法律事務所
当事務所では不動産法務に力を入れています。
当弁護士法人は、不動産トラブル、企業法務、債務整理、離婚、相続、刑事事件など幅広く法律問題に対応しております。お困りのことがあればお気軽にご相談ください。
※記事の内容は執筆された当時の法令等に基づいております。細心の注意を払っておりますが内容について保証するものではありません。お困りのことがあれば弁護士に直接ご相談ください。




