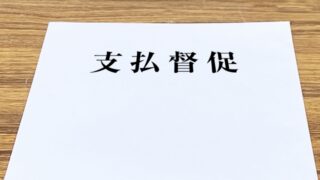目次
物上保証人は債務者の債務を担保する人ですが連帯保証人とは責任の範囲が違います。物上保証人は事業の融資を受けたり住宅ローンを組んだりするときに求められることがあります。本来物上保証人の資格は特にありませんが実際に融資する金融機関により資格が制限されていることがあります。
この記事では、物上保証人について連帯保証人との違いや実際上の注意点などを解説していきます。
物上保証人とは
物上保証人とは、自分が所有する財産を自分以外の誰かの債務を担保するために提供する人のことをいいます。担保提供者などと呼ばれることもあります。抵当権や質権を不動産などに設定することになります。
「保証人」という言葉がついていますが、「物上保証人」と「保証人」は責任に大きな違いがあります。保証人は主たる債務者が支払いをすることができないときは自分が代わりに支払いをする義務(保証債務)があります。しかし物上保証人は特定の財産を担保に提供しただけであり債務を負っていないため、それ以上の支払い義務はありません。つまり担保として提供した財産は失う可能性がありますが、債権者(お金を貸した人など)から残りの債務について支払いを強制されることはありません。
ただし、物上保証人は自分の大切な財産が競売されてしまうのを防ぐために債務者に代わって支払いをすることは可能です。その場合には保証人と同様に主たる債務者に求償することができます(民法351条、372条)。担保権の実行により財産を失ったときも同様です。
求償権について詳しくは、「求償権とは?時効や無視された場合の対処法について解説」をご覧ください。
物上保証人が必要な理由
物上保証人は事業の運転資金や住宅ローンの融資を受ける際に金融機関などの債権者から求められます。お金を貸す方にとっては、物上保証人が土地や建物などの財産を提供してくれれば債務者が支払いできない事態になったとしても債権の回収が可能となり不良債権を防ぎやすくなります。
お金を借りる方にとっては、物上保証人を立てることにより融資の審査に通りやすくなります。金融機関にとっては信用に不安のある方に融資することは難しいですが、債務者の財産や収入のほかに物上保証人の土地や建物などを担保にとることができれば融資しやすくなるからです。
<関連記事>金融機関の審査に通らない理由とその対処法
連帯保証人とは
連帯保証人とは、債務者と連帯して責任を果たさなければならない保証人のことです。通常の保証人の場合には債務者が支払いをしないときにはじめて責任が問題となりますが、連帯保証人の場合には債権者との関係においては債務者と同じ責任を負っているため、債権者から請求を受けたときは拒否することができません。
通常の保証人の場合には債権者から請求を受けたとしても、先に債務者に請求するように要求する権利(催告の抗弁権)や、債務者の財産を差し押さえるように求める権利(検索の抗弁権)があります。ところが連帯保証人の場合にはこのような権利が認められていません。つまり連帯保証人は通常の保証人よりも責任が重いことになります。
債権者として保証人を立ててもらうのであれば必ず連帯保証人にしてもらうようにします。
連帯保証人について詳しくは、「保証人への請求方法|流れや注意点を解説」をご参照ください。
物上保証人と連帯保証人の違い
物上保証人と連帯保証人は責任の範囲に違いがあります。連帯保証人の場合には債務者と同様の責任があるため債務者がローンなどの支払いができないときには債権者は保証債務の全額を請求することができます。
物上保証人の場合には、債務者の債務を担保するためにあらかじめ提供した財産が責任の範囲となります。債務者が支払いを怠ったとしても提供された担保以外に請求を求めることはできません。債権者としては担保権を実行して提供された財産から融資金を回収することになります(物上保証人が任意に債務を弁済することはあります。)。
例えば、抵当権を実行して競売代価から融資金を回収することになります。
<関連記事>不動産競売における換価とは?手続きの流れをわかりやすく解説
物上保証人になるケース
本来、担保提供をしてくれる方であれば親族などに限定されることなく物上保証人となることができます。しかし融資を判断する金融機関は物上保証人となれる資格を一定の方に制限していることがあります。赤の他人が物上保証人となるケースでは詐欺や脅迫などの違法行為の恐れがあるからです。一般的には下記の方が物上保証人として認められています。
親
物上保証人は一般的に2親等以内の親族が指定されています。親は1親等に当たるため物上保証人となれることが一般的です。また義理の親も物上保証人として認められることがあります。
配偶者・婚約者
物上保証人は債務者の配偶者(夫・妻)がなることも一般的です。例えば、事業の運転資金の融資の際に配偶者に物上保証人となってもらうケースです。婚約者については物上保証人として認める所もありますが金融機関により取り扱いが違うため注意が必要です。借り入れを認める場合でも借り入れ実行時には入籍が条件となっていることがあります。
子
債務者の子は1親等の親族のため物上保証人として認める金融会社が多くなっています。しかし子が未成年者の場合には物上保証人として認められないことがあります。親の借金を子の財産で担保する場合、親が子を代理して抵当権を設定することは利益相反行為となるからです。この場合には利益相反となる親の代わりに特別代理人の選任が必要であり家庭裁判所の手続きを要します。
<関連記事>抵当権設定登記とは?費用や手続きの流れを詳しく解説
兄弟姉妹
兄弟姉妹は2親等の親族であり物上保証人として認める金融機関も多くあります。配偶者の兄弟姉妹(姻族)が物上保証人となれるかについては金融機関によって異なります。
同性パートナー
物上保証人として同性のパートナーを認めてもらえることもあります。ただし、法律上の配偶者と同等の関係であることの証明が求められることがあります。
求められる書類は下記のようなものです。
|
・自治体の発行したパートナーシップ証明書のコピー または ・「任意後見契約及び合意契約に係る公正証書の正本もしくは謄本のコピー」、並びに「任意後見契約に係る登記事項証明書のコピー」 |
任意後見契約とは、本人の判断能力が不十分となった場合に自己の生活、療養監護及び財産の管理に関する事務について任意後見人となってもらう契約のことです。
合意契約というのは二人の関係が愛情と信頼に基づく真摯なものであること、共同生活の費用を分担する義務を負うことなどを定めたものです。
祖父母
祖父母は2親等の親族であり物上保証人として認められることも多くなっています。配偶者の祖父母(姻族)が物上保証人となれるかについては金融機関によって異なります。
不動産の共有名義人
不動産が共有状態の場合には全員が担保提供者になることが一般的です。債務者の持分のみに抵当権を設定することは法的に可能ですが、担保権を実行する段階で買い手が付きにくくなるため多くの金融機関は共有名義人に物上保証人となるように求めます。
また、住宅ローンを利用する際に親族の土地に建物を建てるときにも土地所有者に物上保証人になることが求められることが多いです。建物のみに抵当権を設定すると権利関係が複雑となったり担保価値が不十分となったりするからです。
※実際に物上保証人として認められるか否かは金融機関やケースによって異なります。
不動産担保ローンの場合保証人は必要か
不動産担保ローンとは、不動産を担保に融資を受けられるローンのことです。不動担保ローンは原則として保証人が必要ないことが多いです。不動産に十分な担保価値があれば支払いがうまくいかなくても担保権を実行して売却代金から債権を回収できるからです。
ただし、債務者以外の第三者に物上保証人となってもらう場合や収入が少ない場合には連帯保証人が求められることが多くなっています。法人融資のケースでは代表者個人が連帯保証人となることを求められることもあります。
まとめ
・物上保証人とは、債務者の債務を担保するために財産を担保として提供する債務者以外の人のことです。抵当権や質権などの担保権設定者のことです。担保提供者ともいわれます。
・物上保証人は「連帯保証人」ではありません。物上保証人は提供した財産の範囲で責任を負いますが連帯保証人は債務者と同等の責任を負います。
・物上保証人は誰でもなれるのが原則ですが金融機関によって資格が制限されていることがあります。一般的には2親等以内の親族が物上保証人として認められています。
・不動産担保ローンでは保証人が不要なことが多いです。ただし物上保証人については同時に連帯保証人となるよう求められることがあります。
債権回収でお悩みなら弁護士法人東京新橋法律事務所
物上保証人は連帯保証人と異なり責任の範囲が担保として提供された物に限定されています。責任の範囲が既存の財産の範囲にとどまるため担保を取得しやすい一方、担保の価値が低いと債権の回収に支障が出ることがあります。ケースに応じて連帯保証や債権譲渡担保なども検討することが大切です。担保が不十分なケースでは訴訟や強制執行が必要となるため平時から顧問弁護士に相談されることをおすすめします。
当事務所は企業法務や債権の回収に強い事務所です。
顧問契約も承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。
※借金などの債務の返済ができずお困りの方はこちらの記事をご参照ください。