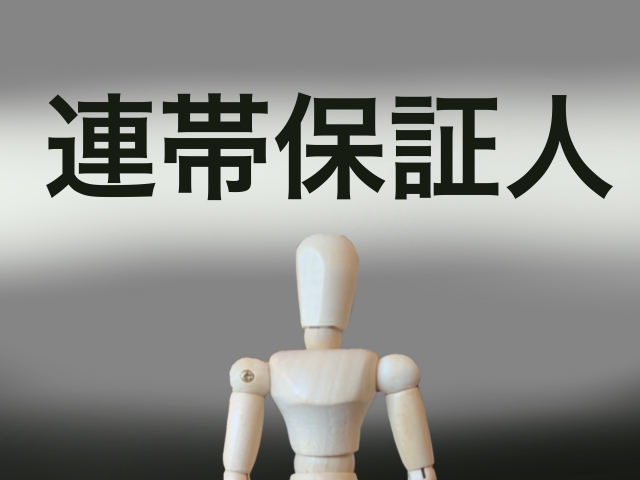
目次
連帯保証人はお金の貸主や大家さん、経営者にとっては思わぬ損害に対処するための防衛策として重要なものです。しかしトラブルが実際に生じたときに連帯保証人が支払いできないのでは意味がありません。連帯保証契約に不備があるときや連帯保証人に資力がないときには債権を回収することができません。
この記事では、連帯保証人について保証人との違いや民法改正による影響などを解説していきます。
※借金などの債務の返済ができずお困りの方はこちらの記事をご参照ください。
連帯保証人とは
連帯保証人とは、主たる債務者(本来責任を負う人)と一緒になって債務を保証する保証人のことです。連帯して債務を保証するため主たる債務者と同様の責任を負います。
もともと保証人は債務者が支払いできなくなったときに補充的に責任を負う立場ですが、連帯保証人の場合には債務者と責任の上では特に違いがないため、債権者としてははじめから連帯保証人に支払いを求めていくことも可能となります。実際にはまず債務者に請求することが一般的ですが請求の順序を気にしなくてよくなるため債権回収のハードルが下がります。通常は保証人といえば連帯保証人のことを指すことが多くなっています。後述しますが債権回収をしやすくする目的で保証人が必要となりますが、連帯保証人でなければ債権回収に手間や時間がかかりやすいからです。
連帯保証人に限らず保証契約は書面でしなければ効力が認められません(民法446条2項)。
連帯保証人になれる人
連帯保証人となる資格は原則として特にありません。ただし、保証人を立てる義務が債務者にあるケースでは、連帯保証人が「行為能力者であること」や「弁済をする資力があること」が求められています(民法450条1項)。
また、ローンや奨学金を申し込む際や不動産を借りる際などに債権者から連帯保証人の資格が指定されることがあります。一般的には下記のような方が連帯保証人の条件となっています。
|
・4親等以内の親族であること ・主債務者の役員であること(主債務者が法人の場合) ・高齢ではないこと ・安定した収入や十分な財産があること ・所得証明書、預貯金残高証明書、固定資産評価証明書等の提出ができること ・日本国内に住んでおり連絡が取れること ・連帯保証人となることの意味を理解した上で承諾していること など |
※上記の要件が必ず必要となるわけではありません。
連帯保証人になれない人
債権者によっては連帯保証人として認めてもらえない方もいます。以下のような方は連帯保証人になれないことがあります。
|
・安定した収入や十分な財産がない人 ・4親等以内の親族でない人 ・自己破産など債務整理中の人 ・生計が同じ人 ・制限行為能力者(未成年者等) ・高齢者(65歳以上等) など |
※ここに示した方が絶対に連帯保証人になれないわけではありません。例えば、高齢者であっても十分な財産を証明することで認められることもあります。
連帯保証人と保証人の違い
連帯保証人と保証人はいずれも主たる債務者の支払い義務を保証することは同じです。債務者が責任を果たさなければいずれも自分の財産をもって返済することになります。保証人が支払いをしたときは主たる債務者に求償していくことができます。
違いがあるのは、「催告の抗弁権」、「検索の抗弁権」、「分別の利益」という権利についてです。通常の保証人にはこれらの権利が認められていますが連帯保証人には認められていないのです。
催告の抗弁権
催告の抗弁権とは、債権者が保証人に債務の履行を求めた際に、「とりあえず債務者に請求してください」といえる保証人の権利のことです(民法452条)。保証人は債務者が支払わないときに代わりに義務を果たせば良いからです。しかし連帯保証人は主たる債務者と連帯して責任を負うため催告の抗弁権が認められていません。
検索の抗弁権
検索の抗弁権とは、債権者が保証人に債務の履行を求めた際に、「とりあえず債務者の財産を差し押さえてください」といえる保証人の権利のことです(民法453条)。保証人は二次的な責任を負う者であって債務者に財産があるならそこから回収するのが基本だからです。ただし、この権利が認められるには条件があり、保証人が、「債務者に弁済可能な資力があること」と、「強制執行が容易であること」を証明しなければなりません。
しかし連帯保証人は主たる債務者と連帯して保証しているため検索の抗弁権が認められていません。
分別の利益
分別の利益とは、保証人が複数人いるケースではそれぞれの保証人は、主たる債務について保証人の数で平等に分割した額についてのみ責任を負うことをいいます(民法456条、427条)。例えば、200万円の債務について二人の保証人がいるときは、各保証人は原則として100万円の責任を負えば足ります。しかし連帯保証人は主債務者と連帯責任を負っているため分別の利益が認められません。
|
|
保証人 |
連帯保証人 |
|
催告の抗弁権 |
ある |
ない |
|
検索の抗弁権 |
ある |
ない |
|
分別の利益 |
ある(例外456条、427条) |
ない |
本来保証人は債務者が義務を履行しないときに責任を果たせばいいはずです(補充性)。
しかし連帯保証人は債務者と同等の責任を負うことを約束しているため分別の利益がなく、補充性もないため催告の抗弁権や検索の抗弁権が認められません。
民法改正による変更点
2020年4月1日に保証人に関する法律の改正がありました。連帯保証人の中には責任の重さを十分に理解せずに契約してしまったり、責任の重さ自体は理解していたものの聞いていた話よりも不利な債務を保証してしまったりするなど連帯保証人の保護が不十分でした。そこで連帯保証人の保護が特に必要なケースで取り扱いに変更が生じています。
極度額のない個人根保証契約は無効
2020年4月1日以降に結ばれる個人根保証契約についてはすべて極度額の設定が必要となります(民法465条の2第2項)。それまでも貸金等債務に関する保証契約に関しては極度額が必要でしたが範囲が広がりました。
根保証とは、一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約のことです。身元保証や賃貸借契約、事業用融資などで利用されます。つまり将来的にいくらの債務になるのかわからないという特徴があります。金額による制限がないと連帯保証人が予期しないような大きな負債を抱える恐れがあります。
そこで個人が保証人となる根保証契約については責任の上限額(極度額)を定めることが必要となりました。極度額は書面で明確に定めなければ効力が生じません(同条3項、446条2項)。
公証人による保証意思確認手続き
個人が事業上の貸金等債務を主な債務とした保証契約を結ぶ前提として、公証人による保証意思確認手続きが定められました((民法465条の6第1項))。連帯保証人となる危険性を理解せずに多額の債務を背負いやすい事業上の融資保証をしてしまうことを防ぐためです。そのため事業と深い関係にある以下のような人たちに関しては手続きが不要とされています。
<公証人による意思確認手続がいらない人>
|
主債務者が法人 |
理事、取締役、執行役等、総株主の議決権の過半数を有する者等 |
|
主債務者が個人 |
共同事業者、主債務者が行う事業に現に従事している主債務者の配偶者 |
連帯保証人への情報提供義務
主債務者が事業のために負担する債務に関して個人に連帯保証人を依頼する場合には、以下の内容についてあらかじめ伝える必要があります(民法465条の10第1項)。
|
・財産及び収支の状況 ・主たる債務以外に負担している債務の有無とその額及び履行状況 ・主たる債務の担保として他に提供し又は提供しようとしているもの |
仮に上記の事項について情報を提供しなかったり、事実と違う内容を伝えたりしたことで依頼を受けた人が誤解をして連帯保証人となった場合には、債権者が情報提供の不備を知っていたり知ることができたときは、連帯保証人は保証契約を取り消すことができます(民法465条の10第2項)。
主たる債務者が契約で定められた義務を怠るなどして本来の支払期限前に一括返済を求められることがあります(期限の利益の喪失)。期限の利益を失えばその分遅延利息も増えてしまうため保証人は思わぬ多額の請求を受ける恐れがあります。それゆえ個人が連帯保証人のケースでは主たる債務者が期限の利益を喪失した場合、債権者は連帯保証人に対し、利益の喪失を知った時より2カ月以内にそのことを通知しなければなりません(民法458条の3第1項)。
<関連記事>保証契約とは?連帯保証契約との違いや民法改正のポイントを分かりやすく解説
まとめ
・連帯保証人とは、主債務者と連帯して保証債務を負う保証人です。つまり債務者と同等の責任があります。
・連帯保証人の資格が指定されていることがあります。一般的には未成年者でないことや安定した収入や財産があること、高齢でないこと、親族であることなどが求められます。
・連帯保証人は保証人と違い補充性がないため「催告の抗弁権」、「検索の抗弁権」が認められません。また「分別の利益」もありません。
・民法改正により個人根保証契約では極度額の定めが必須となりました。
・個人が事業上の貸金等債務を主な債務とした連帯保証人となるには原則として公証人による保証意思確認手続きが必要です。
債権回収でお悩みなら弁護士法人東京新橋法律事務所
当事務所は債権の回収に強い事務所です。
依頼者様のブランドイメージを守りながら債権回収を行います。
当事務所では、未収金が入金されてはじめて報酬が発生する成功報酬制です。
「着手金0円(法的手続きを除く。)」、「請求実費0円」、「相談料0円」となっておりご相談いただきやすい体制を整えております。
※個人間や単独の債権については相談料・着手金がかかります。くわしくは弁護士費用のページをご覧ください。




