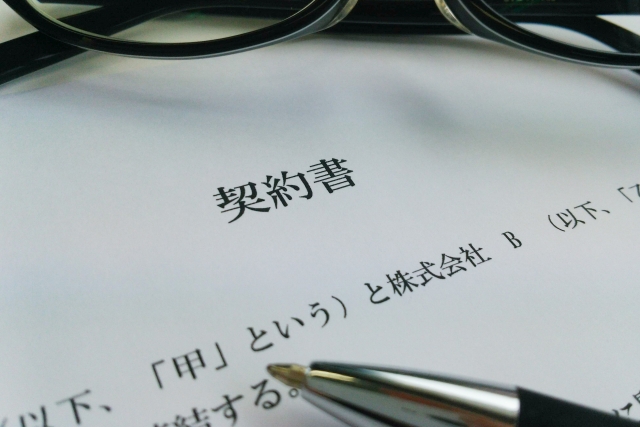
目次
取引先から代金の支払いが遅れているような場合には利息を付してお金を貸しつけた扱いにすることがあります。あるいは何度もお金の貸し借りをしているような場合に一つの契約にまとめ直すこともあります。このような場合に作成するのが準消費貸借契約書です。
この記事では、準消費貸借契約書についてひな形などを含めて解説します。
準消費貸借契約書とは
消費貸借契約とは、当事者の一方が種類や品質、数量の同じ物を返す約束で相手から金銭などの代替可能な物を借り受けることです(民法587条)。普通はお金が対象となります。つまりお金の貸し借りのことを法律上は金銭消費貸借契約といいます。
何かを貸し借りすることについては「賃貸借契約」もあります。賃貸借契約の場合には借りている物自体を約束した期限に返還することになります。ですが消費貸借契約については借りた物自体は「消費」することが予定されており、実質的に同じものを返還すればよい契約です。
例えば、現金を借りたのであればだれかに支払うはずであり借りた物自体は手元にありません。貸主としては貸した物そのものにこだわりはなく実質的に同じものを返してもらえれば満足できる点に特徴があります。
準消費貸借契約とは、金銭やその他の代替可能なものを給付する義務を負う者がいる場合に、その物を消費貸借の目的にすることです。例えば、物を売却したが相手が期限までに代金を支払えないためお金を貸したことにして利息を定めるような場合です。
つまり準消費貸借契約書とは、相手が契約などによってお金を支払う義務がある場合に、そのお金を貸しつけたことにしたことを示す契約書です。
債務承認弁済契約との違い
債務承認弁済契約とは、契約や不法行為などによって支払いをしなければならない義務について確認をし、またどのような方法で支払い(弁済)をしていくのかを約束することです。例えば、慰謝料の支払い義務が相手にある場合に、どれだけの支払い義務があるのか明確にする必要があるときや支払方法(振り込みなのか手渡しなのか分割なのかなど)を定める必要があるときに利用されます。
これに対して準消費貸借契約書の場合には既存の債務を確認することは同じですが、それまでの債務の代わりに新たな債務を生じさせる点に違いがあります。
単なる債務承認や支払方法の変更ではなく新たにお金を貸しつけたとみられるときは準消費貸借契約書を作成することになります。
<関連記事>慰謝料の回収方法とは?請求相手が自己破産した場合の対処法について解説
準消費貸借契約書のメリット
準消費貸借契約書を作成するメリットとして複数の債権債務を1本化できることが挙げられます。例えば、何度もお金の貸し借りをしていたり売掛金が複数生じていたりすると今いくらの債務があるのか分かりにくくなります。そこで準消費貸借契約として一つにまとめてしまえば債権管理が容易となります。
準消費貸借契約書を作成することで債務が明確になるため債務者の自覚を促し支払いをしてもらいやすくなります。
準消費貸借契約書を作成することで訴訟が必要となった際の証拠にすることもできます。また時効対策としての意味もあります。
<関連記事>消滅時効援用における「債務の承認」とは?分かりやすく解説
準消費貸借契約書に記載する内容
準消費貸借契約は、既に存在している債務を消費貸借の目的とするものです。つまり旧債務を新債務に移すことになります。そのため準消費貸借契約書では旧債務を特定しなければなりません。どのように特定するか絶対的な方法があるわけではありませんが、他の債務と誤認しない程度に特定する必要があり、金額やいつ発生したどのような種類の債務なのかなどを記載することになります。例えば、売掛金であれば「〇年〇月〇日から〇年〇月〇日までの〇〇売買契約」などと特定していきます。
お金を貸したことにする金額はいくらなのかを示すため、未払いの残債務金額も記載します。
利息や遅延損害金を記載する際には利息制限法の範囲内でのみ有効となる点に注意が必要です。
債務者の信用状態が悪化した場合に直ちに残債務全額を請求できるようにするために期限の利益喪失条項も重要です。
<関連記事>売掛金の回収に対する利息(遅延損害金)は、とることができるのか?
準消費貸借契約書のひな形
準消費貸借契約は既存の債務を新債務にする重要なものであり書面を作成することが大切です。どの債務が新債務に移るのかが明確でなければ契約が無効となるおそれもあります。準消費貸借契約書のテンプレートを以下に記載します。
<準消費貸借契約書(記載例)>
|
準消費貸借契約書 貸主〇〇〇〇(以下、「甲」という。)及び借主〇〇〇〇(以下、「乙」という。)は、以下の通り準消費貸借契約を締結した。 第1条(既存債務の確認) 甲及び乙は、乙が甲に対して、(〇年〇月〇日付)〇〇契約に基づく債務として、金〇万円の支払債務を負っていることを確認する。 第2条(準消費貸借) 甲と乙は、〇年〇月〇日、前条の乙の甲に対する債務を消費貸借の目的とし、借入金債務とすることに合意する。 第3条(返済方法) 乙は、甲に対し、前条の借入金を次の通り分割し、甲の指定する下記金融機関の口座に振り込む方法で支払う。振込手数料は乙の負担とする。 1 〇年〇月から〇年〇月まで毎月末日限り、金〇万円 記 振込先:〇〇銀行〇〇支店(普通預金)口座番号〇〇〇〇〇〇 第4条(利息) 第2条の借入金の利息は、年〇パーセントの割合とし、毎月末日限り、当該月分を元金とともに支払う。 第5条(期限の利益喪失) 乙は、以下のいずれかの事由が生じたときは、甲から何らの催告を受けることなく、甲に対する一切の債務について期限の利益を喪失し、直ちに元利金を返済しなければならない。 1 乙が第3条の分割金の支払いを2回以上怠ったとき 2 乙が、差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき 3 乙が、破産手続開始又は民事再生手続開始の申立てを受けたとき 4 その他乙の信用状態が悪化したとき 第6条(遅延損害金) 乙は、期限の利益を喪失したときは、期限の利益を喪失した日の翌日から支払済みまで、年〇パーセントの割合による遅延損害金を支払う。 この契約を証するため本契約書2通を作成し、各自その内容を確認し署名押印の上、各1通を所持する。 〇年〇月〇日 甲(貸主):住所 氏名 〇〇〇〇 印 乙(借主):住所 氏名 〇〇〇〇 印 |
必要に応じて連帯保証人や裁判管轄などの条項を入れていきます。
※記載例はあくまで参考です。必ず実際の契約内容に合わせて適切なものを作成してください。自信のない方は弁護士にご相談ください。
<関連記事>契約書作成におけるチェックポイントと注意事項を解説
準消費貸借契約書の印紙税
準消費貸借契約書は印紙税法別表の課税物件である消費貸借契約書に含まれるため収入印紙の貼付消印が必要となります。
債務承認弁済契約書の場合には課税物件にあたらないときには収入印紙が不要です。課税物件にあたる契約で原契約書を作成し印紙税を納付済みの場合には200円の収入印紙が必要とされます。未納付の場合には本来の契約金額に応じた収入印紙がいります。
準消費貸借契約書の場合には、印紙税法別表に記載のある契約金額に応じた収入印紙が必要です(印紙税額一覧表)。
例えば、50万円を超え100万円以下のものは1,000円、100万円を超え500万円以下のものは2,000円が必要です。
ただし、収入印紙の貼付や消印を忘れたからといって準消費貸借契約書自体が無効となるわけではありません。貼付を忘れたときは印紙税の3倍の過怠税が徴収される可能性があります。
※印紙税は令和6年11月18日時点のものです。実際の取り扱いはケースによって異なるため国税庁ホームページをご確認ください。
まとめ
・準消費貸借契約とは、金銭その他の代替物を給付する義務を負う者がいる場合に、その物を消費貸借の目的にすることであり、その内容を書面にしたものを準消費貸借契約書といいます。
・債務承認弁済契約は、既存の債務を確認し弁済方法を定めるものです。準消費貸借契約は利息をつけるなどして新たな貸付債務を生じさせる点に違いがあります。
・準消費貸借契約書を作成するメリットとして、複数の債務を1本化できること、法的手続きが必要となった際の証拠にできることなどがあります。
・準消費貸借契約は既存債務を消費貸借の目的とするため、準消費貸借契約書を作成する際は既存債務を誤認のない程度に明確に特定する必要があります。
・準消費貸借契約書に利息を記載する際は利息制限法の範囲内である必要があります。
・準消費貸借契約書には消費貸借契約書と同じ収入印紙が必要です。
債権回収でお悩みなら弁護士法人東京新橋法律事務所
当事務所は債権の回収に強い事務所です。
債務者が行方不明など他事務所では難しい債権の回収も可能です。
当事務所では、未収金が入金されてはじめて報酬が発生する成功報酬制です。
「着手金0円(法的手続きを除く。)」、「請求実費0円」、「相談料0円」となっておりご相談いただきやすい体制を整えております。
※個人間や単独の債権については相談料・着手金がかかります。くわしくは弁護士費用のページをご覧ください。
「多数の未収債権の滞納があって処理に困っている」
「毎月一定額以上の未収金が継続的に発生している」
このような問題を抱えているのであればお気軽にご相談ください。
依頼者様のブランドイメージを守りながら債権回収を行います。
※借金などの債務の返済ができずお困りの方はこちらの記事をご参照ください。




