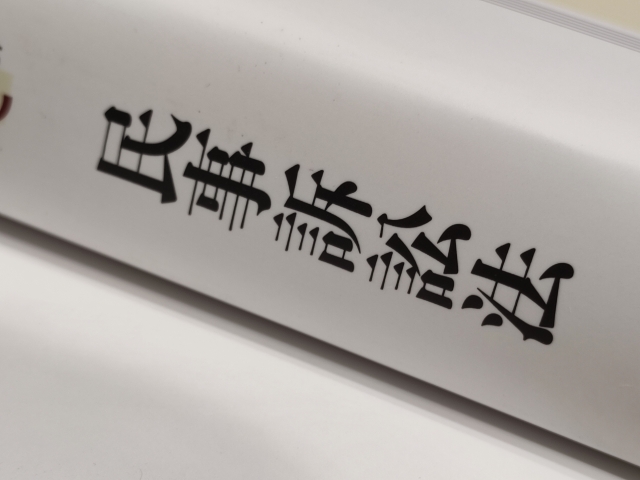
目次
裁判をするには裁判所を利用する際の手数料や弁護士に依頼する場合の報酬費用などがかかります。
この記事では、裁判にかかる費用について目安や誰が負担するのかなどを解説します。
民事裁判にかかる費用
裁判を行うには費用がかかります。民事裁判の費用は「訴訟費用」と「弁護士費用」の2種類あります。訴訟費用は原則として敗訴者が負担するため弁護士費用と混同しないように注意が必要です。
民事裁判の訴訟費用
訴訟費用とは、訴訟のために必要なものとして当事者や裁判所が支出した費用のうち「民事訴訟費用等に関する法律」に規定されているものです。具体的には以下のようなものです。
収入印紙代
訴訟を起こすには手数料を裁判所に支払う必要があり基本的に収入印紙で納めます。手数料分の収入印紙を訴状に貼付しますが金額は訴額によって異なります。窓口に持参する場合には貼付しない方がいいでしょう。過大に納付してしまうと還付手続きが必要となります(民事訴訟費用等に関する法律9条)。消印は裁判所が行います。
<必要な収入印紙>
|
目的の価額 |
手数料額 |
|
100万円まで |
10万円ごとに1,000円 |
|
100万円超500万円まで |
20万円ごとに1,000円 |
|
500万円超1,000万円まで |
50万円ごとに2,000円 |
|
1,000万円超10億円まで |
100万円ごとに3,000円 |
|
10億円超50億円まで |
500万円ごとに1万円 |
|
50億円超 |
1,000万円ごとに1万円 |
例えば、300万円の貸金返還請求訴訟を提起する場合には、2万円分の収入印紙が必要です(100万円部分で1万円、100万円超から300万円部分で1万円)。
郵便切手代
裁判所と当事者との間で郵便物のやり取りがあるため郵便切手も必要となります。事案にもよりますが数千円程度必要となります。
証人の旅費や日当
裁判では証人に証言してもらうこともあります。日当や旅費についても民事訴訟費用等に関する法律で定められています。具体的な金額については裁判所規則の範囲内で裁判所が定めることになっており事案によって異なります。例えば規則で定める日当の上限は8,000円程度となっていますが実際には放棄されることが多いです。
裁判記録の謄写手数料等
裁判記録の謄写には費用がかかります。謄写(コピー)には1枚数十円程度は必要です。
弁護士費用
民事裁判を弁護士に依頼すると報酬費用も必要となります。
法律相談料
弁護士に法律相談をする際には原則として法律相談料がかかります。事務所によって異なりますが大まかな目安は以下の通りです。
|
法律相談料 |
30分ごとに5,000円~ |
※事務所や事案によって無料のこともあります。
着手金
着手金は弁護士に正式に依頼した時点で発生する費用です。依頼の成否に関係なく発生する費用です。以前は報酬基準が定められていて全国一律の金額でしたが現在は報酬が自由化となり事務所によって異なります。しかし旧報酬基準をもとにしている事務所が多いため下記に示しておきます。
<着手金目安>※一般民事訴訟事件
|
事件の経済的な利益の額 |
着手金 |
|
300万円以下の場合 |
経済的利益の8%(10万円~) |
|
300万円を超え3000万円以下の場合 |
5%+9万円 |
|
3000万円を超え3億円以下の場合 |
3%+69万円 |
|
3億円を超える場合 |
2%+369万円 |
※(旧)日本弁護士連合会報酬等基準参考。経済的利益を算定できない離婚事件などを除きます。実際の費用は事務所によって異なり無料のこともあります。
報酬金
事件処理に成功した場合にお支払いいただく費用です。一部成功の場合にも割合に対して発生します。
<報酬金目安>※一般民事訴訟事件
|
事件の経済的な利益の額 |
報酬金 |
|
300万円以下の場合 |
経済的利益の16% |
|
300万円を超え3000万円以下の場合 |
10%+18万円 |
|
3000万円を超え3億円以下の場合 |
6%+138万円 |
|
3億円を超える場合 |
4%+738万円 |
※(旧)日本弁護士連合会報酬等基準参考。経済的利益を算定できない離婚事件などを除きます。実際の費用は事務所によって異なります。
日当
遠方への出張が必要なケースでは費用として日当がかかることもあります。数千円~数万円程度が一般的です。
交通費などの実費
宿泊費や交通費などがかかることもあります。
弁護士費用の相場
弁護士費用は事件の内容によって変わります。費用は事務所によって異なりますが多くの事務所が「(旧)日本弁護士連合会報酬等基準」を参考にしているため目安として示しておきます。
債権回収
相談料
30分5,000円以上が目安となりますが一定の条件により無料となる事務所もあります。例えば、多数の未収金の滞留があったり毎月一定額以上の未収金が継続的に発生したりする場合に無料とするところがあります。
依頼料
着手金や成功報酬費用がかかります。事務所によっては着手金不要のところもあります。裁判ではなく調停や交渉事件として依頼するときには減額されることがあります。
<債権回収目安>※一般民事訴訟事件
|
事件の経済的な利益の額 |
着手金 |
報酬金 |
|
300万円以下の場合 |
8%(10万円~) |
16% |
|
300万円を超え3000万円以下の場合 |
5%+9万円 |
10%+18万円 |
|
3000万円を超え3億円以下の場合 |
3%+69万円 |
6%+138万円 |
|
3億円を超える場合 |
2%+369万円 |
4%+738万円 |
※(旧)日本弁護士連合会報酬等基準参考。実際の費用は事務所によって異なります。
遺産相続
相談料
30分5,000円以上が目安となりますが初回は無料にしている事務所もあります。
依頼料
着手金や報酬費用は遺産の時価総額に対して一定の割合を乗じた金額とするところが多いです。遺産分割請求事件では対象となる相続分の時価相当額が基準です。ただし争いのない部分については時価の3分の1が目安です。遺留分減殺請求事件では対象となる遺留分の時価相当額が基準です。着手金の最低金額を20万円以上としている事務所が多くなっています。
<遺産事件目安>※一般民事訴訟事件
|
事件の経済的な利益の額 |
着手金 |
報酬金 |
|
300万円以下の場合 |
8%(10万円~) |
16% |
|
300万円を超え3000万円以下の場合 |
5%+9万円 |
10%+18万円 |
|
3000万円を超え3億円以下の場合 |
3%+69万円 |
6%+138万円 |
|
3億円を超える場合 |
2%+369万円 |
4%+738万円 |
※(旧)日本弁護士連合会報酬等基準参考。実際の費用は事務所によって異なります。
離婚関係
相談料
30分5,000円以上が目安となりますが初回は無料にしている事務所もあります。
依頼料
離婚交渉・調停の着手金、報酬金はそれぞれ30万円以下が目安とされます。裁判となった場合の弁護士費用はともに40万円以下が目安となります。
<(旧)日本弁護士連合会報酬等基準(参考)>
|
|
調停・交渉 |
訴訟事件 |
|
着手金・報酬金 |
それぞれ20万円~50万円 |
それぞれ30万円~60万円 |
財産分与、慰謝料等の請求は上記とは別に債権回収費用が生じます。婚姻費用や養育費については得られた額の10%程度とすることが多く期間は2~5年分くらいが多くなっています。
<関連記事>未払いの離婚慰謝料の回収方法|強制執行の流れを解説
労働事件
相談料
30分5,000円くらいが目安となりますが初回は無料にしている事務所もあります。
依頼料(従業員)
残業代など金銭請求に関しては「債権回収」に当たります。交渉の着手金としては5万円以上、労働審判は10万円以上が目安です。解雇や労働災害のケースでは高めになり、交渉の着手金は10万円以上、労働審判は20万円以上が目安です。裁判では30万円以上が目安となります。
依頼料(企業)
日本弁護士連合会の実施したアンケートによると懲戒解雇無効の労働仮処分手続きの申立てのケースでは以下のようになっています。アンケートの実施年が古いため現在は高めになっている可能性があります。
|
|
着手金(回答の割合) |
報酬金(回答の割合) |
|
顧問契約がない場合 |
30万円前後(46.1%) |
50万円前後(33.2%) |
|
顧問契約がある場合 |
30万円前後(31.9%) |
20万円前後(31.9%) |
※「アンケート結果にもとづく中小企業のための弁護士報酬の目安(2009年度アンケート結果版)」に基づく
事案にもよりますが顧問契約をしていない場合、総額で80万円~100万円程度が目安となります。
<関連記事>給料未払いの相談先は?弁護士・司法書士・労働基準監督署・社会保険労務士のメリット・デメリット
交通事故
相談料
30分5,000円くらいが目安となりますが無料にしている事務所もあります。当事務所も無料で受け付けております。
依頼料
着手金は10万円以上が目安ですが、無料にしている完全成功報酬制の事務所もあります。損害保険に弁護士費用特約が付いている場合には契約の範囲で保険会社に負担してもらうことができます。
<交通事故目安>※一般民事訴訟事件
|
事件の経済的な利益の額 |
着手金 |
報酬金 |
|
300万円以下の場合 |
8%(10万円~) |
16% |
|
300万円を超え3000万円以下の場合 |
5%+9万円 |
10%+18万円 |
|
3000万円を超え3億円以下の場合 |
3%+69万円 |
6%+138万円 |
|
3億円を超える場合 |
2%+369万円 |
4%+738万円 |
※(旧)日本弁護士連合会報酬等基準参考。実際の費用は事務所によって異なります。
当事務所は着手金が無料となっております。お気軽にお問い合わせください。
※紹介したものはあくまで一般的な目安であり事務所によって実際の費用は異なります。必ず依頼される前に費用をご確認ください。
民事裁判の費用は誰が払うのか
民事裁判の費用の最終的な負担者が問題となります。
訴訟費用は負けた側が負担する
裁判所に納める手数料などの費用は原則として敗訴者が負担します(民事訴訟法61条)。ただし訴訟を遅滞させた場合など公平の視点から勝訴者が全部または一部費用の負担を命じられることがあります。
訴訟費用を具体的に請求するには裁判での負担者と割合が決まった後に別の手続きが必要となります。時間や手間がかかるため訴訟費用が少額のケースでは請求しないことも多くなっています。
弁護士費用は相手方に請求できない
弁護士費用は相手方に請求できないのが原則です。敗訴者に過剰な負担をかける恐れがあるからです。
ただし不法行為による損害賠償金については弁護士費用も損害額に含まれる余地があり、相当と認められる額の範囲で請求できるとされます(最高裁判所昭和44年2月27日判決)。他にも不法行為と同視できる労災や契約で弁護士費用の負担を定めている場合などで請求できる可能性があります。
マンション管理費滞納のケースに関しては、「マンション管理費の滞納を回収する方法|解決策や時効について解説」をご参照ください。
民事裁判の費用を抑える方法
民事裁判はご自身で行うことも可能です。
少額訴訟の活用
請求金額が60万円以下であれば少額訴訟という簡易な訴訟手続きを利用することができます。弁護士に依頼しなければ裁判にかかる費用が少なくて済みます。
<関連記事>少額訴訟のデメリットとは?それでもすべき理由を解説
民事調停を申し立てる
裁判所で話し合いによるトラブル解決を目指す手続きを調停といいます。申立て費用は裁判の半額以下となっています。
<関連記事>債権回収における民事調停とは?手続きの流れを分かりやすく解説
民事裁判費用の負担を訴状に明記する
弁護士費用の請求ができるケースでは明示的に請求していきます。訴訟費用については原則敗訴者の負担となることが法律で決まっているため記載する必要はありませんが、注意的に「訴訟費用は被告の負担とするとの判決を求める」と記載します。
<関連記事>債権回収の弁護士費用の相場とは?相談するメリットや安く抑えるコツを解説
まとめ
・民事裁判の費用は、「訴訟費用」と「弁護士費用」の2種類あります。
・訴訟費用は裁判所を利用する手数料や郵便切手代などがあります。
・弁護士費用には相談料や着手金、報酬金等があります。相談料や着手金は無料のこともあります。
・訴訟費用は原則敗訴者の負担ですが弁護士費用は不法行為などを除き相手に請求できません。
裁判でお悩みなら弁護士法人東京新橋法律事務所
当事務所は法人の方から個人の方まで気軽に相談できる法律事務所を目指しています。
借金問題、債権回収、離婚問題、交通事故、不動産、消費者トラブル、企業法務、刑事事件などに対応している弁護士法人です。
法律のことでお困りのことがあればお気軽にお問い合わせください。




