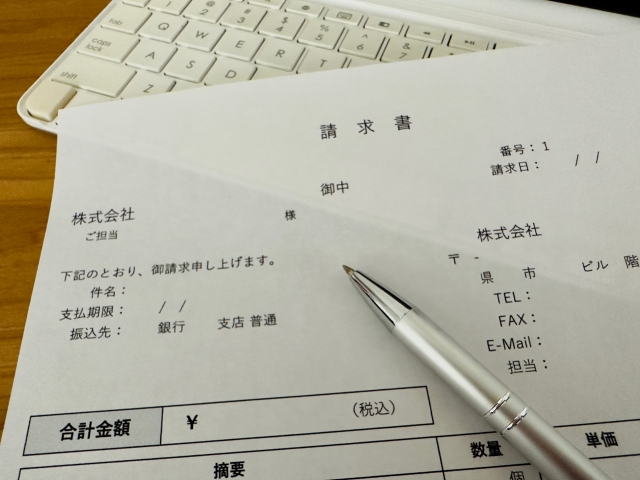
目次
請求書を送付しても入金が確認できず未払いとなることがあります。債権回収は効率よく行う必要がありますがそのためには未払いの理由に応じて催促方法を考える必要があります。
この記事では請求書の未払いが起きた場合の催促方法について解説します。
請求書の未払いが発生する理由
請求書に対する未払いが発生する理由は3つに大別されます。未払いの理由に合わせて催促方法も変わるため原因を突き止めることが重要です。未払いの原因を突き止めるには、①原因の可能性が高いもの、②調査が容易な方法を意識して行います。
自社のミス
未払いが発生した場合にまず疑う必要があるのは自社のミスです。自社の事務処理上のミスが原因の場合には信用にかかわるため早急に対処する必要があります。請求に関わるミスとしては以下の可能性を疑います。
|
・請求書が発行されていない ・請求書は発行されているが相手に届いていない(送付忘れ、宛先を間違えた等) ・支払期日や請求金額に記載ミスがあった |
これらのミスに早期に気付くためには請求書の発行管理を分かりやすくすることが必要です。
<関連記事>請求書を出し忘れるとどうなる?未回収の売掛金を回収するための方法を紹介
取引先のミス
自社にミスがない場合には相手方の事務処理上のミスが原因である可能性があります。取引先に原因があるケースとしては次のようなものがあります。
|
・請求書の処理を忘れていた ・支払済みであると勘違いしていた ・支払期日を誤解していた ・請求書に気づかなかった(迷惑メールフォルダ、他の郵便物に紛れていた等) ・請求書を紛失した |
未払いの原因が取引相手にある際は催促方法に気を使う必要があります。単なる事務処理上のミスであれば催促をすることで支払いに応じてもらうことができますが催促方法が威圧的と受け取られてしまうと別のトラブルの原因となります。
意図的な未払い
未払いの理由として意図的な支払拒否もあります。このケースでは適切な催促方法をとったとしても未払いの解消が難しいことがあります。意図的な支払拒否の理由としては以下のようなものが考えられます。
|
・提供した商品やサービスに不満がある ・詐欺など悪意を持っている場合 ・資金繰りの悪化 |
販売した商品に不具合があるケースでは自社に責任がある限り誠意をもった対応が必要となります。一方で自社に問題がなく不当な利益を得る目的で未払いとなるケースもあります。はじめから支払いの意思がないような悪質なケースでは刑事告訴も含めて厳格な対応が必要となります。
取引先の経営が悪化して未払いとなっているケースでは催促方法を工夫して任意の支払いを促しつつ法的手段も検討します。
<関連記事>請求書の時効はいつ?売掛債権が消滅する期限を解説
請求書の未払いに対する催促方法
請求書の未払いが発生した場合には迅速に対応することが必要です。未払いに備えて催促方法をマニュアル化しておくと効率よく対処することができます。未払いの催促方法は以下のような流れになります。
|
1.請求書に問題がないか確認 2.催促メールや電話 3.催促状の送付 4.督促状の送付 5.法的措置の検討 |
請求書に問題がないか確認
未払いが発生したら請求書の発行・送付に問題がないかチェックすることが必要です。間違いを起こしやすい部分を中心にミスがないか確認します。
|
間違いを起こしやすい部分 |
・発送忘れ ・支払期限 ・宛先違い ・金額の間違いなど |
メールや電話での催促
自社に未払いの原因がないことが確認出来たら相手に確認をする必要があります。ただし自社に未払いの原因がなくても相手に原因があるとは限らない点に注意が必要です。請求書をメールで送付したのであればメールサーバーの不調、郵送したのであれば郵便事故など配送に原因があるケースもあるからです。
普段からメールを使ってやり取りをしている相手であれば催促方法としてメールを利用することが有効です。メールを利用すれば相手方の返信内容が証拠として残りますし労力も押さえられるからです。
電話による催促方法はかける時間帯に制限があることや労力がかかりやすいというデメリットがあります。しかし相手の受け答えをリアルタイムに確認できるため未払いの理由を早期に把握しやすいというメリットがあります。
<関連記事>支払督促・催促メールの書き方とは?押さえておくべきポイントや例文をご紹介
催促状の送付
未払いの催促方法としてメールや電話をしても支払いがなかったり連絡が取れなかったりするケースでは郵便での催促を検討します。
どの催促方法であっても未払い金の支払期限を明確にすることが大切です。期限を設けずに催促するといつまで入金を待てばよいのか判断できないからです。
督促状の送付
催促状と督促状は本質的には同じものです。ただし「督促」という言い回しは威圧感を与えるため未払い期間が長いケースでよく用いられます。相手に心理的な圧力を加える目的や時効期間が迫っているようなケースでは「内容証明郵便」を利用することもあります。
裁判所を利用した手続きである支払督促については、「支払督促について|かかる費用や手続きの流れを詳しく解説」をご参照ください。
法的措置の検討
さまざまな催促方法を講じても未払いの解消がされないときは法的措置を検討することになります。法的措置には以下のような種類があります。
|
・民事調停 ・支払督促 ・仮差押え ・通常訴訟 ・少額訴訟 ・強制執行 |
民事調停や少額訴訟であれば弁護士に依頼せずに済むこともありますが、相手が話し合いに応じない場合や未払い金額が大きい、未払いの件数が多いなど自力での解決が難しいときは弁護士への相談を検討します。
<関連記事>債権回収の裁判(民事訴訟)知っておきたいメリットとデメリット、手続き、流れを解説
催促・督促状の書き方
未払いがあった場合のメールでの催促方法の文例は以下のようなものです。
|
件名:請求書確認のお願い(請求書番号:12345) |
|
A株式会社 〇〇部 〇〇様 大変お世話になっております。株式会社〇〇の〇〇です。 〇月〇日付で発送いたしました請求書(請求書番号:12345)に関して、〇月〇日時点でお支払いが確認できないようです。 お忙しい所申し訳ございませんがご確認をお願いいたします。 なお、本メールと行き違いでお支払い済みであるときはご容赦願います。 |
上記は例文ですので適宜ご変更ください。ポイントは以下の通りです。
|
件名 |
・未払いの催促であることが一目でわかるように ・請求書番号などで未払いの請求を特定 |
|
宛先 |
・法人名や担当部署なども記載 |
|
挨拶 |
・催促しているのが誰か分かるように |
|
本文 |
・未払いとなっていること ・入金確認した日時 ・請求書の送付日時 ・どの請求に対しての未払いなのか請求書番号等で特定 ・支払期限 ・してもらいたいことを明記 |
|
結び |
・入金確認後に支払いがなされていた場合に備えてお詫び ・送信者の名前や連絡先 |
書面での催促状の例文については、「【弁護士監修】支払催促状の書き方と送付方法{テンプレート付}」をご参照ください。
未払いの予防策
未払いを防ぐには以下のような対策が考えられます。
業務フローの見直し
請求不備による未払いの発生を防ぐには請求業務全般の効率化を図る必要があります。そのためには業務の定型化を進めることが有効であり催促方法を手順化したマニュアルの整備が効果的です。
<関連記事>ネットショップで発生する債権とは?債権回収方法を解説
与信管理を厳格にする
与信管理は契約相手や契約内容に合わせて取引の可否や取引可能額を決定してリスクコントロールすることです。取引相手の信用状況を厳格に調査し調査結果に基づき適切な取引限度額を設定しておけば未払いを防ぎやすくなります。
<関連記事>売掛金管理とは?管理の仕方やトラブルの対処法を解説
請求業務にツールを導入する
請求業務を専用のツールに任せることで人為的なイージーミスを防ぐことが可能となり、未払いのリスクを減らすことになります。
未払いが発生した場合には未払い金の回収業務をアウトソーシングする方法もあります。法律事務所の中には未払い金の回収管理システムにより効率的に債権回収できるところもあります。弊所も未払い債権の大量受任に対応した回収管理システムを運用しており効率的に債権回収可能です。
<関連記事>顧問弁護士とは?役割や弁護士との違いを解説
まとめ
・請求書の未払いが発生する理由は、①自社のミス、②取引先のミス、③意図的な未払いに大別できます。理由に応じて催促方法も変わります。
・未払いの催促方法は、メールや電話、督促状の送付などがあります。
・催促しても未払いが解消しないときには法的手段を検討します。ただし弁護士から催促することで支払いに応じてもらえることがあります。
未収金、売掛金の回収でお悩みなら弁護士法人東京新橋法律事務所
当事務所は事業で生じた債権の回収に強い事務所です。
回収管理システムを活用し、大量受任も効率的・迅速に対応可能です。
|
・コンビ二振込票発行管理 ・クラウドシステムからの一括督促(債務者の携帯番号やEメールアドレスの活用) ・自動入金処理 |
当事務所では、未収金が入金されてはじめて報酬が発生する成功報酬制です。
「着手金0円(法的手続きを除く。)」、「請求実費0円」、「相談料0円」となっておりご相談いただきやすい体制を整えております。
※個人間や単独の債権については相談料・着手金がかかります。くわしくは弁護士費用のページをご覧ください。
少額債権(数千円単位)や債務者が行方不明など他事務所では難しい債権の回収も可能です。
依頼者様のブランドイメージを守りながら債権回収を行います。




